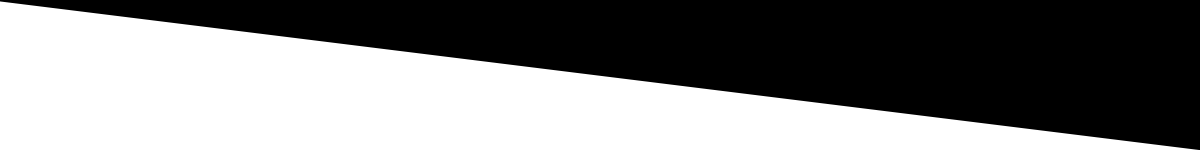
絶対零度にデレはない 一
- Absolute Zero No.1 -
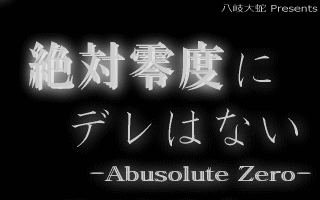
——自分達のクラスに編入生が来るらしい
そんな情報が、僕の所属する二年B組に入ってきたのは、担任教師が朝のHRをするべく教室に現れる目安である、八時二十分を目前にした時のことだった。
高校に入って二度目の夏休みが明け、二学期の始業式も終わり、いよいよ本格的に通常授業が始まろうとしていたこの時期に突然舞い込んできたこの情報は、僕達から長期休暇明け特有の憂鬱な気持ちを一気に吹き飛ばした。
『それ本当かよ!』
『どこから仕入れてきた情報なんだ?』
『夢とかじゃねーよな!』
クラスにいた生徒全員が、その情報を持ってきた委員長の下に駆け寄り、その情報が確かなものなのか確認を取ろうとする。
「あんた達ねぇ……私がガセ情報流すわけがないでしょ?」
苦笑しながら僕達の声に答える委員長。
やや茶色がかった肩の辺りまで伸びた髪をいじりながら、呆れたように首を横に振るこの人の名前は磯密絢音さん。クラスの中の中心的な位置におり、同姓異性問わず人気があって、統率力もある彼女は委員長としては適任なのだろう。
『ま、まぁそうだよな』
『すまん、気を悪くしたなら謝るよ』
ところどころからこんな声が上がる。
「あーいいっていいって。べつに気にしてないから」
そう言って、ひらひらと手刀を横に振る磯密さん。
「でさ、結局の所誰からの情報なの?」
僕は聞いてみた。
「ん?谷園先生から。何か色々な手続きで忙しそうだったから、詳しくは聞けなかったけどね」
「へぇ、そうなんだ」
「相薙もこういうことに興味あったんだね。どっちかっていうと、無関心なほうかなとばかりに思ってたんだけど」
磯密さんは意外そうな顔をして言った。
「いや、僕だって編入生が来るって聞いたら興味くらいは持つよ」
「そう?ごめんごめん」
磯密さんは笑いながら謝ってきた。
相薙とは僕の事で、谷園先生とは担任の事だ。先生も自分のクラスに編入生が来るとなると、嬉しくもあり、慌しくもなるだろう。
気の合う友達はそれなりに何人かいるけど、学校行事などにはあまり積極的に参加しない僕は、磯密さんの目には“編入生が来ても興味関心を持たなさそうな奴”という風に映っていたのだろうか?
「その編入生って……男?女?」
「えっとね……たしか、先生は女の子って言っていた気がするんだけど……」
ふと疑問に思った事を質問してみた僕。すると、磯密さんは少し考える仕草をしてからそう答えた。
その瞬間、クラスの男子から「オォー」という声が上がる。
『ど、どんな子なんだろうな!』
『いや待て。逆に期待しすぎると、裏切られた時のショックは大きいぞ』
『何言ってんだ!そりゃ編入生に失礼だろうが!』
ざわめく男子の様子を眺めつつ、僕は教室の正面にかけられた時計を見た。
「あ、もうすぐ先生くるんじゃ……」
僕がそう呟いたと同時に二つある教室の扉のうち、黒板や教卓や教壇のある方に直結する前の方の扉が開いた。
「ホームルーム始めるぞ。全員、自分の席につきなさい」
教室に入ってきたのは谷園先生だった。穏やかな性格らしく、生徒を怒鳴りつける事もない。ただ放任主義というわけでもないらしく、ルールを守らない生徒にはきちんと指導を入れる先生だ。担当は数学で、裸眼だと両目ともほとんど視力は出ないらしい。
担任の登場に生徒達は一瞬うろたえたが、すぐに一斉に、自分の席へダッシュ。
層の様子を扉の前でじっと見ていた先生。やがて十秒足らずで全員が自分の席へついたのを確認すると、先生は教壇の上に立ち、磯密さんへ目を向けて号令を促した。
彼女の号令に従って朝の挨拶を終えると、先生は言った。
「えー、いつもならすぐに連絡事項を言うのだが、今日は少し勝手が違う」
先生はそこで一旦言葉を切る。教室になんとも言えない緊張した雰囲気が張り詰める中で、先生はこう続けた。
「実は、今日このクラスに編入してくる子がいるんだ。今日は連絡事項を言う前に、さきにその子に自己紹介とかをしてもらう予定になっている」
そう言うと、先生は扉に向かって「入っていいぞ」と少し大きめの声で言った。
ガチャ、とドアノブの回る音がして、扉が開かれる。クラス中のみんなの視線が一斉にそちらに集中する。
入ってきたのは、磯密さんが言っていた通り女子だった。教室がざわめく。僕も正直かなりびっくりした。理由はただ一つ。恐らくクラスがざわめいたのも同じ理由だろう。
その教室に入ってきた女子が、恐らくこれからの人生においてもエンカウントすることは極めて低いと思われるレベルに綺麗だったのだ。
やや伏し目がちに教室に入ってきたその編入生は、腰のあたりまで伸びた、長く艶やかな髪を携えるやや長身でスレンダーな体をしていて、僕の通う学校で女子の規定の制服となっているセーラー服からのぞく肌は健康的で綺麗な肌色をしているし、顔を構成するパーツは、正面から見ていないからよくは分からないが、かなり整っている。凛々しい雰囲気が漂っていて、真面目そうな人だった。
ふと不自然に思った。これだけのレベルの女子が入ってきたとなれば、うちのクラスのノリ的に考えて、一人くらいは喚くなり騒ぐなりする奴(男子)がいてもおかしくない気がする。しかし、教室は依然として静まりかえっている。窓側から二番目の最前列に座る僕は、体をひねって後方の様子を窺った。
——大抵の男子が口をあんぐりと開け、ポカンとしていた。
編入することになったクラスに入ると、クラスの約半数の人間が口をだらしなく開けてお出迎え。彼女にとって、このクラスに対する第一印象が少なくとも良くなる方向に働かない気がするのは僕だけだろうか。
しかし当の編入生さんはそんなクラスの状況などまったく気になっていないらしく、特に何のリアクションも無く(そりゃそうか)教壇に上がって先生の横に並ぶと、彼を一瞥した。
「自己紹介をお願いします」
先生は白いチョークを編入生さんに差し出しながらそう言った。
「……渦美怜香」
編入生さんはチョークを無視して、足下を見ながら自己紹介を始めた。六十六の瞳(クラスの人数は三十三人いるのだ)が一斉に集まると、さすがに恥ずかしいのだろうか。
「……今日から二年B組の一員。よろしく」
心の底から自己紹介なんてどうでも良いと思っているのか、淡々と、面倒くさそうに薄桃色の唇から常套句を紡ぎだすと、彼女は黙りこんでしまった。
僕は不謹慎かとは思いつつも、じっと彼女の事を見ていた。というか、気づかないうちに見惚れていたのかもしれない。別にこれから少なくとも半年間は同じクラスに所属する事になり、いくらでも顔を合わせる機会はあるのだろうけど。
すると幾多もの視線の中から僕の視線に反応したのか、今までずっと下を向いていた渦美さんが、ギロリと鋭い視線をこちらに向けてきた。
そう、ギロリと。
彼女と目が合った瞬間、何か氷の棒でも指されたかと錯覚するくらい背筋が凍った。自分でも、自分の身に何が起きたのか、理解が追いつかない。
鷹に射竦められた小動物のように固まってしまった僕をしばらく無言で見ていた(というか、睨んでいた)渦美さん。そして一瞬目が見開かれたかと思うと、僕から目線を逸らして、次にクラスを見渡した。
クラスの雰囲気が一瞬にして凍った。僕の感覚的な問題なのかもしれないけど。
「えー、渦美も初めてのクラスで緊張しているだろうけど、仲良くするようにな」
唯一、渦美さんの鋭い視線を受けてない先生のいつも通りの声が、クラスに響く。
「……先生、私の席、どこ」
クラスの異様な雰囲気も気にせず、渦美さんはぼそりと言った。
「あぁ、あそこだ」
先生が一番廊下側の、一番後ろの席を指差しながらそう言うと、渦美さんはこくりと頷いて指定された席に歩いていった。
ガタン、と恐らく渦美さんが机の上に鞄を置いた音がする。
その後、先生から連絡事項を数点告げられて、HRは終わった。
先生が教室から立ち去ると、クラスメイト達はそれぞれの自分の席を立ち、自由に行動を始めた。
「相薙、おはよ」
声をかけられたのでそちらを振り返る。そこには中学以来の親友の時雨功太がいた。
「ん、おはよう」
「いやー、あれだな。それにしても、すごい子が編入してきたな」
角刈りの頭をポリポリ掻きながら、時雨は苦笑しつつ言った。
「そうだね。色んな意味ですごいかもね」
「なんというか、他人との関わりを拒絶してるって感じだよな。でも、メッチャ美人っていう。いや、拒絶されても普通話したくなるっつーの!」
時雨は地団駄を踏みながら声を荒げた。誰に向かって怒鳴ってんだよ。
「まぁ、分からなくもない」
笑いながら僕は言った。確かに、今教室の一番隅の席に座って黙々と読書をしている彼女からは、『自分に関わってくるな』的オーラが強烈に発されている。
「あとあの視線……というか、瞳だな。冷たい、とか冷酷、とかでは表せない次元だぜ、あれは」
「あぁ、あれね。確かには怖かった。一瞬というか、しばらく目があったんだけど、背筋が凍ったよ」
今思い出しても若干の鳥肌が立つ。
「背中に氷の鉄筋が刺さった感じが?」
「氷か鉄か、どっちだよ」
「でも大丈夫かなぁ。絶対クラスの奴らから浮く気がするんだけど」
時雨は僕のツッコミをスルーして続けた。
「本人があの調子だから、大丈夫なんじゃないかな?」
「いや、先生から見てどう映るかだよ」
時雨は肩を竦める。
「渦美さんがいじめられてるとか、ハブられてるとか、先生は思わないと思うけど。担任として生徒の粗方の性格は把握してるんじゃないの?」
「そうか……」
真剣に考え込んでしまった時雨を見ていると、ふと深い考えも無くこんな言葉が出た。
「そんなに心配なら時雨が友達になってやれば良いじゃん」
「いや、それは……」
目を泳がせながら口ごもる時雨。
「それとも、一目惚れした相手がクラスで孤立するのが耐えられないとか?」
「な、そそそそんにゃわけないだろうが!」
……動揺しすぎだろうがよ。僕が冷ややかな目線をくれてやると、時雨は、
「ちょ、待って!待ってくれ!頼む!クラスの奴らには黙っててくれよ!自力で少しずつ仲良くなっていきたいんだよ!」
と必死の形相で一気に捲くし立てた。墓穴掘りやがったよ、こいつ。
手を合わせながら頭を下げてくる時雨を軽く流して、僕は席を立つ。
「お、おい!どこに行くんだよ!」
「職員室。今日は日直だから、日誌を取りに行かなきゃいけないんだった」
焦って引きとめようと僕の腕を掴んできた時雨を振り払い、僕は教室を出る。べつに皆に言いふらしに行くわけじゃないですよ。
廊下を歩きながら、僕はふとHRでの一瞬の出来事について考えた。
彼女の冷たい瞳から放たれた、鋭い視線。
そして、一瞬見開かれた目。
彼女の目がなぜ、あれほど鋭く冷たい目をしているのか。そしてなぜ、あれほど他人を拒絶するオーラを出しているのか。
僕が一人で考えた所で答えが得られるはずがないけど、一ヵ月半後にせまる学園祭の事を考えると無視できない問題な気がする。
体育祭と並んで、一番盛り上がりを見せる学校行事の双璧となっている学園祭では、毎年クラスごとに何らかの出し物をすることになっている。
喫茶店とか。射的とか。お化け屋敷とか。
クラスの一人ひとりがそれぞれの役割を担って準備などを進める必要があるけど、渦美さんはその中でどんな役割になるのだろう。クラス一丸となってやることが重要だし、一人だけ浮いている状況はあまり好ましくない気がする。まぁ、学校行事にそれほど積極的でない僕が言っても説得力は皆無だけれど。
……まぁ何とかなるだろう。
そんな無責任なことを徒然なるまま的に考えていると、職員室前についた。僕は今日の晩御飯は春雨が良いなぁ、などと今まで考えてきた事案と全く脈絡のない事を考えつつ職員室の扉をノックした。
[絶対零度にデレはない 一 終]


