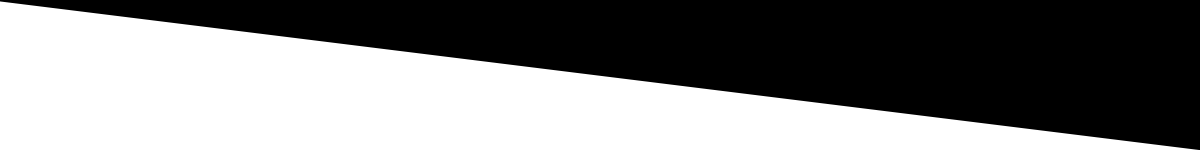
絶対零度にデレはない 八
- Absolute Zero No.8 -
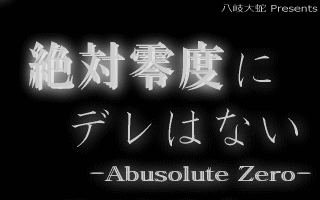
三日後の日曜日の朝。僕は自分の部屋のベッドに横になりながらボーっとしていた。出かける予定は特に無いし、誰かと遊びに行く予定も無い。一日中こうしているのもどうかとは思うけど、たまには良いかななんて思ったりもする。
あれから渦美さんとちょくちょくメールをするのが日課になりつつある。向こうから話を切り出してきた事は一度も無く、全て僕からだが、メールを送ってから必ず十分以内に返信が届くと言うのは今まで一貫している。内容は決まって委員の事や学園祭の事だ。
最初は全く興味が無かったみたいだけど、最近は少しずつだがそうではなくなって来たみたいだ。良いことだと思うんだけど、クラス企画に関する意見や文句は僕に言われても困る。委員長の磯密さんに直接言うように言ってみたけど、どうも話せないらしい。
そう言われてみると、クラスでもまだ孤立している感じがする。今となっては渦美さんに話しかける人は僕と磯密さんを除いては、ほとんどいなくなってしまった。どうせ話しかけても〈絶対零度〉の瞳で冷たく拒絶されるだけだし、というのが大抵のクラスメイトが抱いている考えらしい。これは時雨からの情報。
ちょくちょくメールをするのが日課になりつつある、というのは凄く嬉しいことなのだけど、最近面と向かって話す機会が減った気がする。意図的に避けられている感じではないんだけど、今までより少し素っ気なさが強くなった。必要最低限の会話が終わるとすぐにどこかへ行ってしまう。三日前の携帯のくだりが最近話した中で一番長かったと思う。
あと最近は「二年にメッチャ綺麗な奴が編入してきたらしい」という情報が学校中を回っているらしい。一昨日のメールでは、知らない人から声をかけられたから睨みつけてから走って逃げた、と言っていた。さらに「目と目が合うと動けなくなる」という情報も付属しているらしい。まぁ<絶対零度>の瞳の事だろうし、あながち間違ってはいないんだけど、一応突っ込んでおこう。『メデューサじゃないんだから』と。
そうそう、クラス企画はこの前のHRで時雨案に決定した。次のLHRで景品について深く話し合うことになっている。ある程度のものを用意しておかないと関心を持ってもらえないのは言うまでもないけど、具体的にどんな感じのものにするかは未定だし、その辺りについて議論をするのだろう。
今、十時前だ。何か用事があって忙しくしている可能性もあるけど、暇だったので僕は渦美さんにメールしてみることにした。
『 TO:渦美怜香
本文:おはよう。特に用事が無かったんだけど、暇だったからメールしてみました。忙しくしてたらごめん』
数分後、携帯がバイブする。
『 FROM:渦美怜香
本文:奇遇。私も相薙にメールを送ろうとしていたところ』
あ、そうだったんだ。
『 本文:えっと、何か用事があったって事?もしそうだったら言ってみて』
『 本文:火曜日の放課後、時間があれば少し私に付き合ってほしい』
火曜日の放課後?明後日の事かな?
『 本文:明後日の放課後?全然大丈夫だよ。……何があるの?』
『 本文:直接話がしたい事がある。詳細は現地で説明する』
コンコン、と部屋の扉がノックされる。僕は携帯をポケットにしまった。
「ハル、ちょっと入るよー」
扉が開き、姉さんが入ってきた。
「ど、どうしたの?」
「…………私に何か隠そうとしてる?」
ニコニコしながら姉さんは僕に近づいてきた。怖い、目が笑っていない。
「いや、何も……」
じっと僕の事を見てくる姉さん。僕は、扉から一番離れたところに今腰掛けているベッドがあることを悔やんだ。これではどう頑張ってもこの場から逃れられない。そして、姉さんは僕をベッドの最奥に追いやって、自分が壁になる形でベッドの端に腰掛けた。
「今話してくれたら、右腕一本は勘弁してあげるよ?」
ポキポキと指を鳴らしながら脅迫じみた事を言ってくる姉さん。
「話しても頭と胴体と左腕と両足の保障はないのかよ!?」
「ねぇねぇハルぅ~教えてよぉ~絶対何かあったでしょ~?」
じわじわと距離を詰めつつ、猫なで声で問うてくる姉さん。
「な、何もなかったってば」
「今話したら、もれなくヤンデレモードになってあげるよ?」
「怖いよ!ならなくても良いよ!」
「私のハルに近づく女は許さない。ハルは私のもの、私はハルのもの。汚らわしいメス豚どもがハルに近づこうなんて、一億光年早いわ。ハルは一生私と一緒。ねぇ、この前話していた、赤い服を着たツインテールの中学生の女の子は一体誰?私がいるのに、何で私以外の女と話したりするの?私の全てを私はハルに捧げているんだから、ハルもハルの全てを私に捧げてくれてもいいじゃない!私は、私達は!天国に行ってもハルと一緒。私とハルとの関係は永遠に……」
「ちょ、姉さん!僕何も話してないよ!?っていうか、ジリジリと距離詰めるの止めてもらえるかな!マジで怖いから!あと、僕の知り合いにツインテの中学生とかいないから!」
目が逝きかけている姉さんをこっちの世界に引き戻す為に、姉さんの肩を必死に揺すっていると、ポケットに入れていた携帯がバイブした。
「あ、メール来たみたいだよ?」
姉さんが僕のポケットを指差して言った。
「そ、そうだね」
「ん?どうしたの?見ないの?」
曖昧に笑って誤魔化そうとする僕を見て、姉さんはなるほどねー、とか呟いた。
「ターゲッ・トロッ・クオーン!」
「ぎゃー!ポケット目がけて突っ込んでくるな!それと、わざわざ促音の直後で区切る意味が分からないから!」
「相手は誰だ!お嬢様か!病弱っ娘か!女教師か!バニーガールか!委員長か!眼鏡っ娘か!巫女さんか!メイドさんか!電波か!ボーイッシュか!スク水かぁぁぁぁ!」
「姉さん落ち着いてよ!っていうか、最後だけ人間じゃないよ!」
「もしやっ……あのロリっ娘かぁぁぁぁ!」
「分かった姉さん!見せる!見せますから!だからお願い、落ち着いて!」
半泣きになりながら懇願する僕。
「わーいわーい」
「早いな、おい!僕の発言から一病弱で正座+良い子モードとか、レベル高すぎだね!」
ベッドの上でビシッと背筋を伸ばして正座をする、ニコニコ笑顔の姉さんに声を荒げた後、姉さんを警戒しつつ、僕はポケットから携帯を取り出してメールを見……
「もらったぁ!」
気づいた時には、遅かった。僕の手元から携帯は忽然と姿をくらまし、姉さんが僕に背を向けて電子音を……って何あれ、光!?今、僕の目の前で、光速レベルの何かが!
「…………」
あれ?姉さんが固まった。様子が変だぞ?
「ほう、これは……へぇ……」
「ちょっと、何なのさ。見せてよ」
僕に背を向けて勝手に人の携帯をいじっている姉さんに抗議の声を上げる。
「はい」
姉さんは印籠を前に突き出すように、携帯の液晶画面を僕に見せてきた。
『 本文:返信が来ないので、繰り返す。火曜日の放課後、二人だけで話がしたい』
「渦美って……あのクーデレっ娘かぁ!」
「ま、まぁね……」
「んーでもその子って、ハルがロリっ娘に鞍替えした時にモーレツに嫉妬して、ヤンデレ化したんじゃなかったっけ?」
チグハグな事を言いながら不思議そうに首を傾げる姉さん。
「してないからね。事実を捏造しないでね。ヤンデレ化はさっきの姉さんだから」
「感動した!まさかここまでハルが成長するなんて!」
僕の言うこと聞いてないよ、この人。
「……ど、どういうことさ」
「いくら鈍感なハルでも分かるでしょ?二人で直接話したときに、どんな話が切り出されるかくらいはさ」
僕は頭をかきながら、うーんと唸った。
「告白系のフラグに決まってるでしょ!」
「そ、そうとは限らないんじゃ……」
眉をひそめる僕に、姉さんは「例えばね」と言いながら、人差し指を一本上に向ける。
「『右利きだから好きでした!』とか」
「利き腕って好感度左右するの!?」
「『男だから好きでした!』とか」
「なにその不特定多数感満載な理由!」
「『男の頃から好きでした!』とか」
「本格的にリアクションに困るね!」
姉さんからまともな意見を期待した僕が馬鹿だった!
「でも内心、こういう展開はちょっと期待してるでしょ?」
「うっ……」
たしかに、ちょっとは期待してるかもしれない。渦美さんは全くそんな素振り見せた事ないけど。あ、男の頃から~とかはもちろん論外だし、ありえないけど。
「当たり前でしょ」
笑いながら姉さんは言った。
「そんな素振りを迂闊に見せるほど、女は馬鹿じゃないのです」
どうやらまた心の中を読まれたらしい。
「でも……初めて会ってから、まだ三週間くらいだよ?絶対早すぎると思うけど……」
「そこは引っかかるけどね……でも、他に何か思い当たる事ある?」
「……今は何も」
「なら、一番妥当な案というか、流れで決定じゃない?」
姉さんは足をバタバタさせながら言った。
「うーん、まぁその日になってみないと分からないよなぁ」
僕は姉さんの意見に頷く事が出来ずに考え込んだ。姉さんは、そんな僕見ながらニコニコ笑うだけだった。
さて、月曜日になった。
「おっす相薙。元気してるか?」
教室にて、自分の席に突っ伏しながら、つかの間の安息に身を寄せていた僕は、聞きなれた声に呼ばれて体を起こした。
「おはよう。元気元気」
そう返すと時雨はニカッと表情を崩しながら、
「そう来なくっちゃな!」
と言った。
「今年ももうすぐ終わりだな~」
「まだ九月じゃん」
「色々なことがあったよな」
どこか遠い所を見ている時雨。
「何かあったわけ?」
「いや、そういう訳じゃないんだけどな。なんかこう、気分がメリークリスマス&ハッピーニューイヤーって感じなわけよ」
いつも平和で良いな、時雨は。
「いや、そんなことよりさ」
「何?」
「お前、最近渦美と何かあったか?前と比べると話している時間が少ない気がするけど。喧嘩か?へへへ、ざまーみろ」
おーい、最後の方、心の言葉が漏れてるぞー。そういう事は、直接本人に言うもんじゃないだろ。……しかし、時雨の目にもそう映っていたのか。
「うーん、そうかな?」
とぼけておく事にした。
「そうかい。でも、それにしてもお前凄いよな。クラスで唯一あの絶対零度を手懐けているんだもんな。レベル高すぎだろ」
「手懐けるは止めろ、手懐けるは。普通に話してるだけだし」
「学年男子の中ではトップクラスの里坂でさえ、撃沈したんだぜ?」
里坂とは2年F組に所属してる男子生徒のこと。スポーツは万能だし、成績も常に上位に食い込んでいるし、百二十六人いる二年男子の中でもかなり格好いい方だ。そういえば水泳部のキャプテンを務めて気がする。女子の間ではファンクラブがあるとかないとか。
「撃沈って……里坂くんも渦美さんにアタックしたの?」
「みたいだぜ。あいつから動くなんて珍しいのにな。で、返ってきた言葉は『……べつにあなたと交流を持つ気になれない』だとさ。食い下がったら例の通り<あの>瞳が里坂を射抜いたわけだ。それでもニコリと笑いながらその場を立ち去ったって言う噂だから、アイツすげーよな」
そう言って時雨は肩をすくめる。渦美さんの真似が若干似ていたのに驚き。
「そ、そんな事があったのか」
「その渦美を手のひらの上で弄んでるんだから、お前ってスゲーよ」
「絶対わざとでしょ。わざと表現を誇張してるでしょ」
バレたか、と言いながら時雨は笑う。
「でも、あれだぜ。そろそろ気をつけた方が良い頃かもしれないぜ。渦美とお前の関係を勘繰る動きも出てきてるから。フラれた奴からすれば、お前に対してガソリンに火をつけたレベルで羞恥心をメラメラと燃やしているだろうからな」
神妙な調子で時雨は言った。
「嫉妬心ね。べつに恥ずかしがる事はないと思うから」
「だから、とりあえず気をつけておけよってことだ。これは親友Aからの忠告だ!」
ビシィ!っと僕を指差す時雨。まぁ時雨の言いたい事はなんとなく分かった。でも、正直言って実感が湧いてこないんだけど……
「うぉぉおおおお!」
突然、僕の顔面めがけて拳が飛んできた。相手は言うまでもなく時雨だ。間一髪でそれを首の動きだけでかわし、いきなり何するんだと抗議の声を上げようと彼を睨むと、曰く〝羞恥心〟にメラメラ燃えている目がそこにはあるわけで……
「(実感が)湧いた!湧いたぁぁぁ!」
傍から聞くと、さぞかし不可思議な会話だったろうと思う。「うぉぉおおおお!」「湧いたぁぁぁ!」とか普通あり得ないよね。
僕はしばらく時雨に追いかけ回された後、いい加減ムカついて来たので彼の肩に軽くパンチを入れてやろうと拳を振るったのだが、これが予想以上に効いたらしく、時雨は肩をおさえて教室を転がる、転がる、転がる。
その、傍から見たら「大丈夫かこいつ?」的な姿を視界の隅で確認しながら、彼がのたうち回ってくれている隙に、僕は教室から脱出することにした。
[絶対零度にデレはない 八 終]


