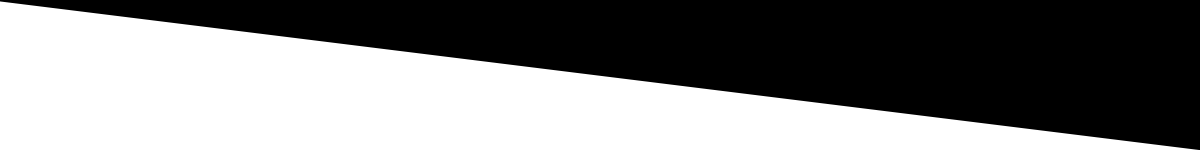
隙間5センチからの音色
- Tone from the Gap -
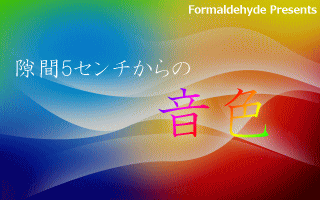
――僕は、長い夢を見た――
地面をきゅっ、と掴み、掴んだと同時に今度は地面を突き放す感覚で体を押し上げる。これを交互に繰り返すだけで、人は疲れを感じる。いくら疲れるな! と言い聞かし、なだめすかしても、呼吸は荒くなり、体が重くなる。吐き気がして、足が震え、ぶっ倒れる。
「なっさけねーな」
頭の上で聞き覚えのある先輩の声がした。と、思うと同時にドンッと顔の横に足が振り下ろされ、僕は反射的に目を瞑り、首を竦めた。薄目を開けた時、先輩が振り向きざまに意地の悪い笑みを向けているのが見えた。先輩の巻き上げたていった砂粒を顔から払い、僕は片足を立てて座り直した。
ここの陸上部は強い。学校名は全国にとどろき、卒業生はその多くが当たり前な顔をしてスポーツ界で活躍している。中には、先輩を初めて見たのはテレビの中、なんて事もある。
『強いから』という理由で僕はここに入部した。それは、弱い者が強いものに憧れるというある種の必然に沿ったもので、それは腕の細い子が凶器に惹かれたり、力の無い大人が酒に頼ったりする事と似ている、と思う。そう考えると、先の凶器に走る子よりも、坂道を走る自分のほうが幾分か健全じゃないか。と一人勝手気ままに考えを巡らした。そんな不出来な新入部員の隣を、邪魔さ半分、苛だたしさ半分といった表情の他の部員が次々と走り抜いていった。
「おい、どうした。怪我か?」急に後ろから野太い声がして、僕は内心舌打ちをした。顧問を務める体育教師の一人だ。
「おい、何してるんだよ。走れよ」
言われてから僕がなんの支障も無く立ち上がったのを見て、先生の声に少しどすが利いた。
「あ、はい。すいません」
僕が即席で靴をはき直す仕草をすると、「さぼるなよ、新入部員」と言い残し、先生は先に坂を上っていった。その後ろ姿を僕は卑怯ににらみつけた。それからふと、視線をあげて、すぐ目の前、僕の高校の白い校舎を見上げた。
サッとなにかが動いた。そんな気がした。場所は三階一番左。僕の目の前で、ちょうど音楽室のある窓の奥だ。そのほとんどがクリーム色のカーテンで締め切られ、そのカーテンとカーテンの合わせ目のわずか数センチの奥でそれが見えた。気がした。今は薄暗い隙間にしか見えないため、てっきり見間違いかと思ったが、もう少し注意深く見ているとそのカーテンが不自然にもぞもぞと揺れていて、これはやはり誰かいるな、と思った。
「おいっ!お前!走れって言ってるだろ!」
今度はごまかせなかった。僕はとたんにバネ仕掛けのおもちゃのように飛び出した。
それから数週間、陸上部の練習に『ばっくぐらうんどみゅーじっく』がかかるようになった。部員たちは練習中にその音楽が流れるとあからさまに嫌な顔をし、特に練習用に使う高校前の長い坂に面している例の音楽室の前では耳までもふさぐようになった。
そんな大不評の音楽の演奏者を、僕は知っていた。普段はカーテンの奥に隠れていて姿が見えないのだが、間違い無い。『あの日』、カーテンの陰に隠れたあの人物だ。
「ったく、うっせーな」
練習が終わって更衣室に帰ってきた時、先輩が愚痴っているのが聞こえてきた。
「ほんと。もっとうまくなってから吹けよ。トランペットだよな、あれ」
別の先輩が返事を返した。
「しらねーけどさ、そういうの。でもありゃねーな。かすれたり妙に高い音出したり」
「先生もあんなのに楽器持たせるなよな」
「ほんとな」
僕はただ黙って横から話しを盗み聞きするだけだった。そこに加わることも無ければ異議を唱えることもなかったが、彼らの言葉はもっともなことに思われた。下手くそが吹くな。心の中でそう思った。
更衣室を出るとまたあの切れ切れの音の欠片が聞こえてきて、僕は思わず笑ってしまう。改めて聞くとやはりひどい。
校舎に近づくにつれて音は大きく、より鮮明に聞こえてきた。カーテンの隙間5センチからはときどき低いブォという音や短く切ったような高い音など、さまざまな音が聞こえてきて、単にうるさいと感じる思いと、次はどんな突拍子もない音が飛び出すかと期待する思いも生まれた。おそらく必死になって音を出そうとしているのだろう。そういった息づかいもその隙間から一緒に聞こえてくるようだった。
その後の部活では例の演奏者について話題が多く出るようになった。一つにはもちろん下手という事もあるが、一番の要因は『姿を見せない』という事だろう。カーテンの奥にいて決して姿を見せない、ある意味で有名な演奏者に会ってみたい。そう思うのは人として自然な流れだっただろう。特に、一瞬だけチラッと見たことのある僕の気持ちは日に日に募っていった。だから雨で陸上部の練習が休みになったとき、僕はこっそり音楽室に向かっていた。
ブオ、プッ、プゥー。
防音用に引かれたドアのカーテンの向こうで、今日もトランペットの音が聞こえた。情けなくはあるが、それでも毎日練習している分、自分よりは幾分か健全じゃないか。僕はそう思い、思ってからようやく、そうか。僕の姿もこれに負けず劣らず情けなかったのか、と気付いた。ようやく気付けた。
ここまで近いと、トランペットの音に混じって、微かに力む声も聞こえてきた。ああ、女子か。簡単に判別がついた。その微かな声は男子にしては力がなく、幼く感じられた。
不意に、窓のそとの雨が気になった。しとしとと降り続ける雨はいつまでも降りやまないような粘り強さを感じさせた。
つまらない。
僕はもう一度ドアを見つめた。興味はある。でも急に、ドアを開けてまでその女子を確認したいとは思えなくなった。僕の気持はここで『半端』だった事に気付いた。それにどう言って用事もない音楽室のドアを開ければいいのかもわからない。だから実際、僕は踵を返し、本当に音楽室に背を向けた。
事情が変わったのは、ガチャリ、という音と共に、音楽室のドアが開いた事だ。思わず振り返ると、そこにはトランペットをくわえた女子生徒がひょっこり顔だけを突き出していた。
「あ、えと、あの、音楽室に用ですか?」慌てて楽器から口をはなした女子生徒は、今度は怪訝そうに僕を見た。仕草は可愛らしいがそう思うより先に問いに対する言い訳が頭に並ぶ。
「あ、あぁ、ええと、それは……それは……」
頭に思いつく言い訳が喉にひっかかって出てこない。おい、どうした。何してるんだ? 怪我か?
女子生徒はただ黙って僕を見ていた。眉をひそめるでもなく、拒絶の眼差しを送ってくる事もなかったが、その純粋な疑問を浮かべた瞳が余計に僕を焦らせた。それなのに言葉はますます喉の奥に引っ込み、気付くと僕はただただ酸欠の金魚みたいに口をパクパクさせていた。
はっとして口を閉じた時にはもう遅い。女子生徒はそれを見ると今度はその純粋な瞳を大きく見開き、それから急にその目を伏せると押し殺したような笑い声を出した。
「な、何?」
急に不安が襲ってきた。
人に笑われる事には昔から敏感だった。最も嫌いな事だと言ってもいい。それも、とくに異性に笑われると、まるで喉の奥にコンクリートを流し込まれ、内臓を固められた気分になる。それから冷たい感覚がジワジワと全身に行き渡り、そこから急性の鬱にも似た症状に変わる。自分はなんてくだらないのかという類いの自己否定から全身の倦怠感、虚脱感に変わる。
僕は彼女を見た。まだ顔を俯けて笑っている。前髪の小刻みな震えとトランペットの鋭いちらつきがやけに目障りだった。
こんな所、来なければよかった。そう思い、急にすべての事柄が腹立たしくなった。自分の事、陸上部の事、その顧問の教師の事、雨で中止になった練習、音楽室の前の自分、目の前で遠慮も知らずに笑う女子生徒、目障りなトランペット、醜い自分、それから……。
「可愛い……」
笑いにかき消えそうな震えた声がどこからかした。俯いた顔が上がった。頬が幾分か上気していて、そこに二つ、三日月状のえくぼができていた。
「すいません、なんか仕草が可愛かったから。」
よほどツボに入ったのか、そう言って彼女はまた目尻を下げ声を押し殺して笑い続けた。そんな彼女を、僕は半ば呆れた顔であらためて見た。
それから……、失礼じゃないのか? 急性鬱症候群の患者は退院ぎわに愚痴った。
音楽室は大して他と代わり映えもしない、フツーの音楽室だ。いや、むしろフツー以下だ。防音もしっかりされてない壁に、歪んだ机。設置されているスピーカーも、校長が胸を張るほどの安物だし、どことなく広く見えるのは単に場所をとる楽器が無いためだ。
女子生徒に案内されて座ったのは窓際に設えられた机だった。女子生徒は近くから椅子を引きずり寄せ、トランペットを内ももに挟む形にして座った。
「で、」ひとまず落ち着いてから女子生徒が切り出した。
「ここには何の用?」
ああ、と僕はスラリと言った。どこかで、体のどこかがチクリとしたが気付かないフリをした。
「音楽の先生に呼び出されたんだ。職員室にいなかったんだけど……」そう言ってぐるっと教室を見回してみる。そこには教員どころか二人以外には人一人いない。もちろん、音楽教員がいないのは百も承知の上での嘘だ。男子として、人気の無い教室で女子と二人っきりというのは世間一般的にチャンスなのだろうが、残念な事に僕にはそれを楽しむ余裕も勇気もない。僕からすれば、ここは単に息苦しいだけでしかなく、先方には悪いが、さっさと嘘を並べて早くここを抜け出たかった。
だが、女子生徒はまるで人の嘘を聞いていないように見えた。そっぽを向き、その瞳が真剣に見えたので、釣られて僕も振り返ってみたが、あるのは壁に掛けられたベートーベンの仏頂面だけだった。しばらくして、
「まあさ、嘘はいいから」ぼそりと、ごく自然につぶやいた。それから女子生徒は視線をまた僕に戻した。その眼の瞳孔に、呆気にとられた僕の姿がくっきり映っていた。
「で、今日は部活、無いんだ?」女子生徒は淡々と、どこかしら非難するかのような口調でそう尋ねてきた。その目は黒く、表情は無い。思わず、僕の体がビクリと震えた。
「ぁぁ……う、うん。雨だし、体育館も使えないから……」
「そうなんだ」そういって女子生徒は黙りこくった。
額にジットリと脂汗が滲んでいるのがわかった。嘘を嘘と見抜かれた事よりも、むしろその後の淡々とした ――まるで血の通っていないような――機械作業のような口ぶりが怖かった。
それはまるで、死体と話している感覚だった。
「あ、あのさ」黙っている事のほうが余計に怖かった。その黒い瞳が毎秒毎秒僕の内面を洗い出し、無言の内に僕が隠した記憶を認識している気がした。
「なら、どうして僕を教室に入れたわけ? 僕がここに用が無い事……知ってるんでしょ?」こんな相手に嘘をついても意味が無い。女子生徒は否定しなかった。ただ小さく、ぼそっと「……いい調子」と聞こえた気がした。
「え?」
「初めて見たとき、あなた嘘ついてた」女子生徒はそこでフッと無表情をやめた。嘘のように消えた表情の後に、なにかを懐かしむような顔付きが生まれた。
「……あの時、僕の事見てたって事?」
なんとか話を取り繕う。先ほどの言葉の通りなら、僕が怒られた時、やはり彼女はカーテンの奥から僕の事を見ていたのだろう。なんだろう。なんか、少し恥ずかしかった。
「うん」
彼女はその時の事を心から楽しんでいるように見えた。声のトーンも徐々に明るくなる。
「いきなり先生の声が〝ヤクザ〟になったから、おもわず見たら丁度怒られてた」そう言って彼女はまたおかしそうに笑った。僕自身も、彼女の言い回しがおかしくて笑った。いや、彼女が笑ってくれたことで、初めて自分も笑っていいのだと認められた気がして、笑った。
ひとしきり笑いあったことで二人の間の壁が無くなった気がした。雨は相変わらずことことと降りしきり、それに反応しているかのように彼女の前髪も柔らかくさらさらと流れた。
「ところで名前、なんていうの?」彼女は真っ直ぐ僕を見つめて言った。
「佐藤」名乗ると、彼女はなぜかおっ、と声を上げ、うれしそうな顔をした。
「え?」
「ううん。私は田中っていうの。ほら、ありきたりな名前じゃない。お互い」
「あ、そういうこと……」ようやく僕は納得した。ありきたりな名前は、持った者でないと気持ちはわからない。本来は苦痛な自己紹介も、お互いありきたりな名前だったため気後れもなく、どことなく安心感があった。
「そっか、陸上部か」思い出したかのように田中が言った。
「ここの陸上強いもんね。将来はアスリート選手とか?」
「いや……」僕は言葉を濁した。〝ただ『強い』という言葉に引かれただけなんだ〟なんて言葉はあまりにも稚拙に感じられた。田中はただ、ふーんと言ったきりでなにも言わなくなった。
「そ、そっちは吹奏楽部なんでしょ?」僕がぎこちなくトランペットを指さし言うと、田中はそこでようやくトランペットの存在を思い出したかのように眼の高さまで持ち上げた。トランペットの開いた口の暗さとボディの輝きが対照的で、金塊のようなずっしりとした存在感があった。そこに歪んで写る田中の顔はその逆に、あまりに弱々しかった。
「うーん。まあね」
そこで田中は僕と同じように言葉を濁した。申し訳なさそうにまたトランペットを下げる。
「いっつも聞こえてるでしょ?私の練習」
「うん。聞こえてる」僕は自然と先輩達の会話を思い出した。
――『ったく、うっせーな』
『もっとうまくなってから吹けよ』
『先生もあんなのに楽器持たせるなよな』
『下手くそが吹くな』――
最後の声は自分の声だった。突拍子の無い音を嘲笑っていた、自分の声……。
「……うるさい?」田中はすまなさそうに僕を見上げた。僕は田中を見つめ、一度口を開いて、閉じた。
あのとき、盗み聞きした言葉。あのときはただ黙って聞いていた。その言葉が正しいと、卑屈な自分は感じていた。
でも、
――うるさくても必死に努力する他の部活と、途中でばてて靴をはき直すふりをする部員のいる自分の部活。誇れるのはどっちだ……?
――そもそも、楽器も触らずに楽器が上達するだろうか……?
――先生にも、なにかしらの考えがあるのだと、そう思わなかったのか……?
――お前は何様だよ。おい、自分。
あれ? そんな風に考えて、一番驚いたのは僕自身だ。いままで自分でもわかるほど卑怯な考え方しかできなかった僕が、どうして急にこんな雄弁な、正論を言えるようになったのだろう。まるで自分にもう一つの人格が形成された気分だった。
僕は驚いて田中を見返した。
「ん?」 どうかした? 僕の変化を敏感に感じた田中はころんと首を傾げた。彼女は自覚していないのか、それともわからないフリをしているのか。僕には区別がつかなかった。それほどまでに、彼女は役者だ。
まぁ、いいさ。細かい事はどうでもいい。今は、彼女の問いに対してこの言葉を贈るのがなによりも先だ。
「かっこいいよ。」
「えっ?!」僕の言葉に、田中は高い声をあげた。
「か……かっこ……いい?」
うん。僕はにっこり笑って頷いた。
「下手でも、苦手でも、がんばる姿っていうのはやっぱりかっこいいよ」
ぼくもそうなりたいよ。君みたいに。これは内心で付け加えた。
田中は、しばらくしてから驚いた顔を緩めた。
「わかった?」
ああ、わかったよ。それにこの意味は、おそらくぼくら二人にしかわからないはずだ。いや、そうであってほしい。
後ろを振り返った。5センチの隙間から見える雨はだいぶ止み、今は小雨程度に収まっていた。これのどこに雨粒を絞り出せるだけの湿気があるのかと疑問に思うほど空は雲一つ無く澄み渡っていて、これで、あそこの山のあたりから虹でも架かっていたらきれいだろうなと思ったが、『現実』はそう簡単にはいかなかった。
天涙の景色が、カーテンとカーテンの間で短く、長く、切り取られていた。そこから射す陽光はそれまで日陰で育った僕にはあまりにも眩しく、そして――
――ボクは、メをサマシタ。
最初に見えた光景は部屋に取り付けられた電灯から蜘蛛の糸のようにのびる紐と、そのすぐ隣で揺れるクリーム色のカーテン。そのカーテンの下の空いた隙間から溢れる朝日が寝ている僕の顔に降りかかっていた。膝を立てて起き上がり、僕は手で顔を拭った。ジットリとした感触だった。太陽の登りが早い夏は朝日といえど熱量が別格だった。体を起してみると見慣れた六畳の自分の部屋が目の前に、ある。目につくものはどうしようもなく本当に見慣れた物ばかりで、急に馬鹿らしくなった。
僕は寝ていたベッドの端に座り直し、うなだれた。
――夢……――
僕は静かな所作で自分の手を前に突き出し、その両手をジッと眺めた。握力が十も無い手。懸垂で一度たりとも踏ん張れない手。それは自分が自分であることの目に見える証拠。自分は『強い』だとか『勇敢』なんて言葉にほど遠い存在であるという暗示。
全てがフィクション。全てが夢物語。
夢の中で気付いていても可笑しくなかった。中学生の僕がどうして高校などに通っているのだ。あんな高校は見たことがないし、陸上部の強豪校なんて貧弱な自分には関係が無い。――おそらく、あの高校は実在しない、僕の勝手な妄想の産物なのだろう。
そして――
あの、トランペットの少女も――
「………ッ!」
開いていた手をギュッと握った。両の手から血の気が失せ、白んでいくのが見て取れた。
――心に穴が空いた。文章でしか見たことのない言い回しに襲われた。
はは
自然と溢れる笑い声。そもそも『心に穴が空いた』なんて可笑しいじゃないか。一時の夢という、実体のない『物』をねじ込められ、無理矢理空けられたんだ。よくよく考えれば非科学的だ。でもそれなのに、いやだからこそ、誰も攻められない。だって穴を開けたのは仮にも自分だから……。
その日は結局中学校へは行かなかった。ドアに施錠し、母の呼びかけはことごとく無視した。母は不登校の理由をしつこく問いただしたが、昼近くになり、捨て台詞のように お前なんか知るか。一生そこにいろ。と、吐き捨て、2階の僕の部屋から遠ざかっていった。僕はそれからも相変わらずベッドに座り、カーテンの隙間から見える、なんの代わり映えもしない向かいの家の庭を勝手にのぞき見ていた。いくらか時間もたっていて、幾分冷静にはなっていた。少なくとも今では学校をサボった事や、母への八つ当たりも申し訳無く思えるぐらいには気持ちが和らいでいた。
だからだろう。さきほどから声が聞こえる。
『下手でも、苦手でも、がんばる姿っていうのはやっぱりかっこいいよ』
去り際の台詞が何度も何度も頭の中でリフレインする。木霊の如く遠ざかり、木霊とは違いまた近づいて来る。自分の言った言葉がまるで自分の言った言葉に感じられない。まさしく木霊のように、誰かが代わりに言った言葉のように思えてくる。
また自分の手を見つめる。だって、僕はそんな勇敢さとは無縁の人間として生まれたんだから。こんな事言ったはずが無いだろう? ああそうだ。この手を見るといつも思い出される。自分の弱さ。卑屈さ。自分への嫌悪感。嫌悪感。嫌悪感。嫌悪感、嫌悪感、嫌悪感、嫌悪感嫌悪感嫌悪感嫌悪感嫌悪感嫌悪感―――!
――――嫌悪感?
何だろう。何かがひっかかる。つい最近、こんな気持ちになった事がなかったか? 既視感が科学的にも精神的にも解明されてない以上、僕にできるのは、ただ覚えている記憶を探るだけだった。
無視する事もできたはずだ。いや、そもそも既視感の出所をわざわざ探る人間なんて聞いたこともない。でもなぜか思い出さないといけない気がした。使命だ。義務だ。僕に欠けていた行為だ。
朝に見ていた夢はとうに朧気な残像と化している。思い出したとたんに崩れ去りそうな記憶を必死に押さえつつ、僕はそれを丹念に調べていった。それでも、もう半分も思い出せない。夢の忘れやすさは異常だ。
――『可愛い……』
すう、と。記憶の海から、一つの言葉が浮かび上がった。それに釣られるように、その言葉の前後の記憶が蘇る。
虚構の世界の陸上部が雨のため、中止になったあの日、僕は最初で最後、彼女に会いに行った。陸上部の僕が、放課後に用事があるはずも無い音楽室の前に立っていた。彼女は不思議そうに僕に問いかけた。
『あ、えと、あの、音楽室に用ですか?』
とっさに、卑怯な僕は言い訳を並べた。でも、不思議だった。その言い訳を、〝彼女に対してつきたくない〟と思ったのだ。
結果、なにも言えずに黙ってしまった僕を見て、彼女はおかしそうに笑ったんだっけ……?
僕は勘違いをした。かっこいい事なんて何一つできやしない僕は、昔から人に笑われるのが一番嫌いだった。だから、僕は自分が笑われたんだと思い、急に自分自身が嫌になった。夢の中ですらまともに人と接することができない、非力な僕に失望したんだ。だからこそ……
『可愛い……』
そんな言葉、今までかけられたことがあっただろうか……? 可愛い? え、可愛い?
嬉しかった。はじめて自分の存在が認められた気がした。かっこいい事ではないかもしれないけど、可愛い事はできた。上出来じゃないか。
僕はその時、物心ついてはじめて『嫌悪感』から解放された。そうだ、解放されたんだ。
――その僕が今、『嫌悪感』を抱いている。
はは
自然と溢れる笑い声。
なんで、そんなことを感じる必要がある?
僕は醜くない。劣っていない。それを、彼女が教えてくれたのに、なにを今更憂える必要がある……?
馬鹿らしい
そこまで考えた時だった。
ブオ、プッ、プゥー。
僕はハッとして身を固くした。カーテンの隙間5センチから見える外の世界に目を凝らし、トランペットの音色に耳を澄ませた。そこに、もう一度。
ブオォ、プゥー、ピー。
瞬間、僕はベッドから飛び降りた。洋服ダンスを開け、目についた服を引っ張り出し、急いで着替える。内心、朝から無気力を口実にパジャマのままだった自分を恨んだ。袖口で指を二度ひっかけ、一度ジーンズを前後ろ逆さに履いた後、部屋のドアの施錠を解き、ドアをダンッと言わせて押し開けた。階段がジェットコースターに変わる。驚いた顔で台所から顔を出したお母さんは、おもしろい顔をして飛び出す小人のようだ。靴をつっぱり掛けで履き、玄関を勢いよく開けた。
夏の昼の日差しが、日陰で育った僕に射した。眩しい。暑い。でも、明るい。暖かい。僕は自ら光を求めるように走り出した。地面をきゅっ、と掴み、掴んだと同時に今度は地面を突き放す感覚で体を押し進める。アスファルトの道路はほんの少ししか地面に接しない足を確実に焼いていった。向こうに見えるのは、細分化されていく住宅街と海。それと堂々とした入道雲。
僕は立ち止まり、耳を澄ませる。トランペットの音色はまだ聞こえる。その事にほっとしてまた走る。
川沿いの道に出た。小さいながらも自営業の店が軒を連ねる、この住宅街でのメインストリートだ。平日の昼間に出歩く数少ない歩行者は、路地から弾けるように飛び出した僕に驚き、身を引くようにして道を譲った。その中を、僕は全力で走った。不思議と息は切れなかった。まぁ、それもそうか。僕はアスリート選手を何人も生んでいる陸上部の部員だったんだから……!
ブーゥ、プッ、プ。
おい、どこにいるんだよ、田中。
プーー、プァー、ブゥ。
僕、初めて自分に自信が持てたよ。それも、君のおかげだ。このことを、一番に君に伝えたいんだ……!
パーン、パパーン、パパパパーン!
僕、君に会いたい。どこにいるんだよ。からかうなよ。
トランペットの音色が小刻みになる。トランペットをくわえたまま笑っている。そういう音だった。
笑うなよ。たしかに台詞はちょっと女々しいけどさ、でも……それを可愛いって言ってくれたのは君じゃないか。
がむしゃらに走って着いたのは、住宅街の中心にある、広い空き地だった。何年も前から地元の小学生の遊び場になっている場所で、僕は今その真ん中に一人で立っていた。さすがにこれだけ走ると肺がキリキリと痛む。心臓が体の中心で脈動するのを体で感じられた。顔からは次々と汗が雫となって滴り落ち、足下の土の色がそこだけ濃くなった。何度も何度も肩で息をしながら、僕は体を捻って周りを見渡した。いくら走ってもトランペットの音はつかず離れず、どこか遠くから鳴り響いていた。トランペットを吹きながら、僕の走りに付いてきた? いや、それは不可能だろう。そもそもそれなら今僕の近くにいるはずだ。だが、見通しのいい空き地には、そんな人影は見当たらなかった。
なら……
僕は自然と自分の胸の上に手を当てた。とくんとくん、と脈動する心臓の鼓動。汗で湿った有り合わせのシャツの感触。それともう一つ、指先に伝わった。
――あはは、驚いた?
ビュッ、と突然巻き起こった突風が、広い空き地を舐めるように吹きわたった。半袖のシャツから伸びた僕の細い腕に、舞い上がった砂利がピシピシとぶつかる。同時に、いたずらっ子のような快活な笑い声が響く。僕はふぅ、と息を漏らし、弱々しく微笑んだ。嬉しさを噛み殺し、目を閉じ、思考する。
驚くに、決まってるだろ。
二回目、突風は次に背後から吹き付けた。突風は、汗を吸ったシャツをもはためかせ、僕を追い越し、その前線に木の葉を乗せたまま空き地を滑るように進んだ。そしてぐるっと一周してから僕のすぐ目の前でぐるり、と急激な渦を巻き、入道雲の湧き上がる夏の空へと溶けた。
僕は胸に手を当てたまま、その空を仰ぎ見た。祈りにも似た仕草だった。目の前には、青い空と、そこにとけ込む彼女が見えた。夏の日差しを涼しげに透かして、僕を真っ直ぐに見つめる彼女が。これは決して幻想では無い。夢では無い。理由なんていらない。理屈なんていらない。ただ、彼女がここにこうしていてくれる。それだけでよかった。
――それだけで、幸せ。
田中は微笑んでいた。光に透けた彼女は、美しいとともに、どこか儚い。
そんな様子に、思わず口を挟みかけた僕を、彼女は優しい視線で制した。それから田中はプイと空を見上げた。それから、どこか懐かしむような口調で言った。
――ありがとうね。『かっこいい』って誉めてくれて。
『下手でも、苦手でも、がんばる姿っていうのはやっぱりかっこいいよ』
それは、僕が初めて本心から言えた本当の言葉。生まれて初めて、自分に自信が持てた時の言葉。誰よりも先に、なによりも先にまず彼女に伝えたかった言葉。
なんだよ。僕は呆れた。結局、僕らは互いが互いを救っただけだったのか、と。
――嫌悪感にまみれた僕を、彼女は『可愛い』と言って慰めた。
――夢の中の君を、僕は『かっこいい』と言って励ました。
おあいこじゃないか。貸し借り無しだ。じゃあ、と。僕は言いたい言葉をこっそり心の中で変えた。
これからも、よろしくね。
その言葉で、彼女ははっきりとわかるぐらいに赤くなった。
――ちょ、やめてよ、突然。恥ずかしいでしょ!
彼女はそう言って僕の頭をポカリと殴りつけた。痛みも感触も無かったけど、あったとしても僕はそれを痛いとは思わなかっただろう。
彼女は照れ隠しのためなのか、またトランペットを取り出し、高らかと音色を吹き立てた。
パッパカパーン!
高く、気高い音が、僕と彼女だけが居るこの空き地に鳴り響いた。三回目の突風が巻き起こった。二人を取り囲むようにして生まれた風に、音符のような木の葉が混じる。風は吹き、音が風に乗り、舞い上がる。音符が僕と君の周りをドーム状に巡り、陽光を受けて輝きを増す。音が舞踏し、合唱する。音が音を生み、それがかち合ってさらに音を生む。はてしなく、いつまでも、どこまでも、音色が生まれる。
そんな世界を見て、僕はこっそり誓った。
いつかきっと、絶対、君に本当に言いたかった言葉を面と向かって告げられるような、そんな立派な自分になってみせるよ。だから、今はまだ、心の中でこっそりと言うよ。
気付かせてくれて、ありがとう。
それから……
――好きだよ――
[ 隙間5センチからの音色 完 ]


