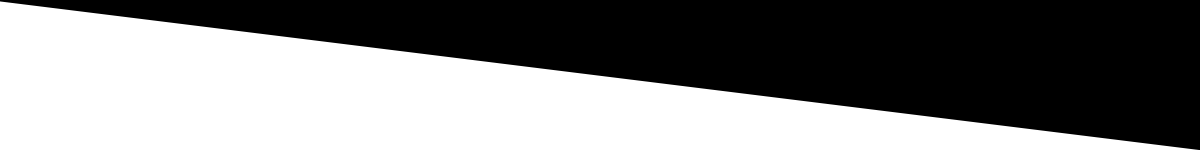
蜜柑
- Mikan -

コンセントを抜かれた冷たいコタツに突っ込んだ足が何かに当たった。くいくいと器用にその物体を足で引き寄せる。コタツに掛った布団を持ち上げ、中を覗いていると、足の間に丸い輪郭が現れた。コロコロと転がり現れたのは一個のミカンだった。洞窟にも似たコタツの口から、不意にその明るい色を見せたミカンは、余力を抑えきれずに、太ももに当たってようやく止まった。
そのミカンは、よくコタツの上に盛ってあるような手のひらサイズの小さなものではなく、大きめのリンゴほどの大きさがあり、手に取るとずっしりと重い。へたの部分の実がふっくらと盛り上がっているのでデコポンに近いのかもしれない。柑橘系の持つ、苦さと酸っぱさを混ぜた匂いがする。
そのミカンを、まるで神様に奉納するかのように、暗い部屋の中で持ち上げる。閉ざした窓の隙間から入り込むわずかな日の光を、艶のある橙色の皮が跳ね返す。こうして見ると、まるで夜空に浮かぶ月が大きな腕に捕まえられている様にも見える。そういえば、月は恒星だったっけ、なんて事が思い浮かんだ。
思い浮かんだと同時に、指を皮に掛け、力の限りに皮と薄皮の間に爪を食い込ませた。分厚い皮は果実とは思えないほど堅い。それでも力ずくで皮を剥いてゆく。皮から弾ける汁が、スプレーのように細かい粒子となって噴き出されているのが見えた。
ミカンを支える手も、蜜柑を剥く手も、次第にその細かい粒子を浴びて濡れてゆく。しばらくするとそれは水滴になり、ツーっと右手の手首を伝い滴り落ちた。ぶわっと、蜜柑の匂いが急に増す。ツンとした苦い臭いが鼻をついた。
そうして皮を剥き終わった頃には両手には何本ものすじが静脈の様に走り、ナメクジの這った後のようにテラテラと光っていた。噴き出た汁が目に入ったのか、目が痛い。挙げたままだった両腕には倦怠感もある。それでも、その両腕の先には皮の剥けたデコポンが握られていた。白い繊維が濡れた手に絡みつく。
しばらくの間、皮の剥けた月を仰ぎ見た。
それから、その球体をゆっくりした動作で包み込み、その両腕にぐっと力を込めた。
ぶしゅ、という音で、球体の内部がぶちりと派手に断裂したのが伝わった。同時に指の隙間から、行き場を失った果汁が勢いよく噴出した。それでも手に掛かる力は緩まず、それどころか叙々に力を増していった。
手の内で、果実がひしゃげ、果汁が噴き出し、薄皮が千切れた。そして、集まった果汁は手首の裏の細い隙間から、滝の様に滴り落ちた。
その滝を目を閉じ、口を開け、喉の奥に流し込む。まるで蛇のように、常に形を変えて降る蜜の滝は、口だけでなく、時には首元や顔にも容赦なく降りかかったが、なぜだか、やはりこれも止める気にはならなかった。
真っ暗な8畳の部屋に、一縷の月光が差しこんだ。
[ 蜜柑 - Mikan - 完 ]


