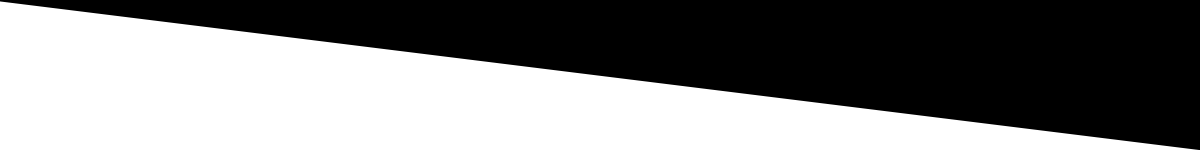
絶対零度にデレはない キオクノカケラ
- Absolute Zero Prologue -
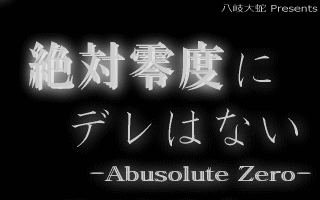
「ねぇねぇハルくん!」
「どうしたの?りんちゃん」
「わたしたち、ずーといっしょだよね」
「そうだね」
「しょうらいは“けっこん”するんだよね」
「うーん……よくわかんないや」
「すーるーの!わたしとハルくんは、しょうらい“けっこん”するんだよ?」
「そうなのかな?」
「ねぇねぇハルくん!」
「どうしたの?りんちゃん」
「………………」
彼女の口から次の言葉がなかなか発せられない事に、僕は不安を感じた。
「どうしたの?」
僕がもう一度問うたその時、僕以外の体温が僕を包んだ。
「……りんちゃん?」
いきなり僕に抱きついてきた彼女に少し戸惑ったが、僕はなんとか平静を保った。
「……ずーと、いっしょよね?」
僕はガタガタ震えた。違う。僕に抱きついている彼女が震えていた。
「うん、ずーっといっしょだよ」
「ありがと」
僕がそう答えると、彼女は嬉しそうに笑いながら言った。そして、僕の頬に何かが触れた。最初、それが何か分からなかった。
「……え?」
「やった、いただきっ」
「あ、え、ちょっ……」
僕は、一瞬遅れて頬に触れたものを認識した。彼女の唇が、ちょこんと遠慮がちに当てられたのだ。
「ねぇねぇハルくん……」
「ど、どうしたの?りんちゃん」
「……わたしのこと、わすれないでね。わたしも、ハルくんのこと、ぜったい、ぜったいにわすれないからね」
彼女の言った意味が分からなかった。いきなり何を言い出すんだ、と問いただそうと僕が口を開きかけた時、彼女が僕から離れた。
「り、りんちゃん!まって!」
僕はとっさに彼女を呼び止めようとする。しかし、彼女は走っていってしまった。
僕は突然の出来事に頭がグチャグチャになり、何が何だが分からなくなって、彼女を追いかける事もせず、呆然とその場に立ち尽くしていた。
——相手の顔も話した場所も、覚えていない。
——朝だったか、昼だったか、夕方だったか、夜だったか、それすら分からない。
——そんな曖昧なキオクノカケラ
——ただ、はっきりと思い出せることが三つだけある。
——その日、一日中凍えるような寒さだったということ。
——“りんちゃん”という子が、右腕に鈴のついたリストバンドをはめていたこと。
——この会話の数日後に“りんちゃん”という子が行方不明になったこと。
[絶対零度にデレはない キオクノカケラ 終]


