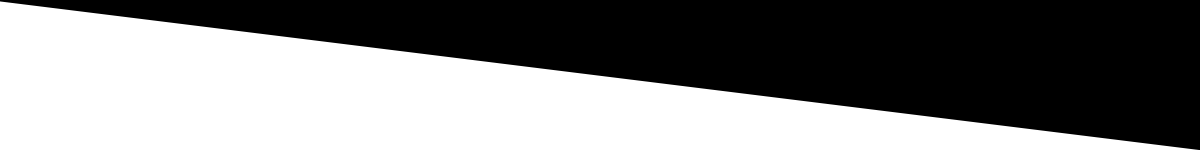
絶対零度にデレはない 十
- Absolute Zero No.10 -
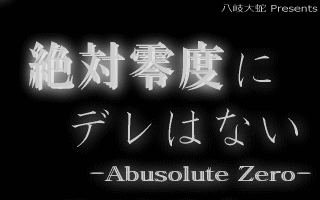
バタン、とタクシーの扉が閉まる。渦美さんは運転手に聞きなれない場所を告げると、それきり目を瞑って黙り込んでしまった。
「えっと……渦美さん?どこに行くつもりなの?」
「……行けば、分かる」
「いや、そんな、心の準備が……」
うろたえる僕をチラリと横目で見ながら、渦美さんは
「……大丈夫」
と小さく呟いた。
大丈夫と言われてしまっては返す言葉がない。僕は不安な気持ちを押し殺して、平静を保ちつつ黙ってタクシーに揺られることにした。
しかしまぁ、凄く貴重な体験をしていると我ながら思う。こんな密室の中で、すぐ横には恐らく学校で一、二を争うレベルの女子高生が座っているのだ。あ、意識したらなんか緊張してきた……
しばしの沈黙を破ったのは、優しそうな初老の運転手さんだった。
「しかし……あそこに行かれるとは珍しいですね。私はもう何十年もこの職をさせてもらっていますが、ここ数年は一度も行っていませんね」
「……そう」
話す相手がタメ年でも、後輩でも、初老でも、渦美さんの相槌は変わらない。
「昔は活気のある場所だったらしいのですが……今は何もない所ですし、あると言えば、大きな公園くらいですかね。ただ、管理が全く行き届いていないせいか、遊具の老朽化が深刻化しているらしいです。危険ですから、誰も近づかなくなってしまったようですね」
「そうなんですか……えっと、ここからだとどれくらいの距離になるんですか?」
僕が尋ねると、運転手さんは少し考えてから僕の質問に答えた。
「……ここからですと、そうですね。大体二十〜二十五分程度で着きますよ」
意外と遠いな。汚い話になるけど、お金とか大丈夫なのか?誰が払うんだろう?
「……大丈夫、私が払う」
僕の気持ちを察したのか、渦美さんは言った。何か申し訳ないかも。
「まぁ、あそこに行くと言う事は、色々とワケありなのでしょうが……」
いや、ワケありも何も、僕渦美さんと知り合って一ヶ月位なんですけど。というか、自分でもどんな所に行くのか分かっていないんですけど。
「……べつに。大した事じゃない」
渦美さんは窓から外の景色を眺めつつ言った。そして再び車内に沈黙が流れる。
僕は静かに目を閉じた。タクシーのエンジン音だけが聞こえてくる。瞼が重くなってくる急に睡魔が襲ってきた。起きていても特にすることはないので、僕はその睡魔に呑まれることにした。
「…………ぎ」
誰かが僕の肩を叩いている。意識の遠くの方で、何か声が聞こえる。
「…………いなぎ」
さっきよりも強く肩が叩かれた。恐らくグーだ。痛い、そこ鎖骨なんですけど。
「……相薙っ」
右の頬につねられた様な痛みを感じ、僕の意識は覚醒した。
「えっ、あ、えっと……」
「……ついた」
うろたえる僕を、運転手さんが苦笑しながら見てくる。
「お代はもう戴きましたから、お兄さんが降りませんと、お嬢さんが降りられませんよ」
「あ!すみません!」
いつの間にか半開きになっていた扉を開けて、僕は慌てて外に出た。渦美さんもそれに続いて降りてくる。運転手さんは「この辺にはタクシー乗り場はありませんからね。三十分くらいならここら辺でウロウロしておきますよ」と言って何処かへ行ってしまった。
着いた所は、大きな広場のような場所だった。中央には大きな噴水台があるが、水は噴き出ていない。その噴水の周りには幾つかの長いベンチが置いてある。
運転手さんが言っていた遊具とはアレのことだろうか。中央の噴水台から少し離れた所に、黒く錆ついているジャングルジムや滑り台、大半が腐っている木で出来たシーソーなんかが置いてある。
辺りは閑散としており、僕たち以外誰も人はいない。なんで渦美さんはこんな所に僕をつれて来たのだろうか。
僕たちはベンチまで歩いた。渦美さんが適当な所に腰掛ける。僕もその隣に失礼する。
「……ここは、私にとって思い出の場所」
渦美さんは俯きながらポツリと言った。
「……小さい頃は、ここら辺でよく遊んだ」
「そうなんだ……」
「……相薙の思い出の場所、ある?」
渦美さんの言葉が、疑問形になった。
「思い出の場所……か」
僕は考えに耽ってみる。思い出の場所……
「ごめん、ちょっと思いつかないな」
僕は頭をかきながら言った。
「…………そう」
渦美さんはいつも通り、素っ気なく返してきた。でも、いつもより間があったのは気のせいだろうか?僕は渦美さんの方を窺った。
一方では<絶対零度>の瞳を持つ少女として恐れられ、しかし他方ではかなりの美少女として注目を浴びている彼女の表情は、数ミリ単位のレベルでしか変化がない。知り合ってまだ少ししか経っていないし、偉そうな事は言えないけれど、そう思う。
「渦美さん、ところでさ。今日ここに僕を呼んでくれた目的って何?」
僕はタクシーに揺られていた時から、いやもっと前……昨日メールをもらった段階から抱いていた疑問を、改めて彼女にぶつけた。
渦美さんは遠い所を見ながらじっと口を噤んでいた。しばらくして、やがて彼女の白桃色の唇が開かれ、言葉が紡がれた。
「……相薙に、伝えておきたい事があった」
僕は、緊張で渇ききった唇をなめた。昨日の姉さんとのやり取りを思い出す。この雰囲気、この緊張感、もしかして姉さんの言っていたことは当たっていたのか……?
「……少しだけ待って。二分くらい。……気持ちの整理がしたい」
「う、うん」
僕が返事をすると、渦美さんはベンチから立ち上がり、入り口とは反対側に広がっている林の方へと姿を消した。
「はぁ〜」
完全に彼女の姿が見えなくなったのを確認して、僕はここ数年で最も深く大きなため息をついた。なんかこう、息の仕方を忘れるくらい気を張っていたのだ。
僕はベンチにごろりと横になって、夕焼けに染まっている空を見上げた。その状態から深呼吸。人気はないし、点在している遊具の老朽化はかなり進んでいるけれど、空気が凄く綺麗で、気のせいか、いつも地元で吸っている酸素より美味しく感じられた。
するとその時、人が歩いてくる音がした。あれ?まだ三十秒も経っていないぞ?
いや待てよ、渦美さんは確か入り口とは反対側の方向に行ったはずだ。でも、今聞こえてくる足音は、入り口の方から聞こえてくるではないか。……まさか僕たち以外に誰かが来るとは思ってもみなかった。
やがて足音は僕の横で止まった。そちらを見てみると、まず視界に入ってきたのがチェック柄のスカートと茶色の靴……革靴かな?視点をもう少し上げてみると、何処かの高校の制服だろうか、藍色のセーラー服、そしてもう少し上げてみると……
「やっぽー」
屈託のない笑顔でこちらを見てくる一人の少女の顔があった。僕は体を起こす。
「ど、どなたですか?」
聞いてみる。すると少女は泣きそうな顔になって、
「ひどーい!忘れちゃったんだぁ!」
と言った。
「うぅ〜……ひどいな〜!ひどいな〜!ショックだなぁ〜!」
顔を両手で覆いながら体をクネクネさせる少女。いや、指の隙間からこちらの様子をチラチラ窺ってるの、丸見えだから。
僕はベンチから起き上がって、伸びをしながら、彼女のことを改めて観察した。
年は……僕と同じくらいかな?背は少し低めだけど、中学生には見えない。明朗快活、という四字熟語がしっくり来そうな明るい雰囲気を持っている。
「あれれ?どうしたの、難しい顔してさ」
何でこんなに馴れ馴れしいんだろう。そう言えば、さっき彼女は「忘れちゃったの?」とか言ってたな。もしかして本当に昔あったことがあるのか?
「もう、何があったの?私にも教えてよ〜」
考え込んでいると、彼女はさっきまで渦美さんが座っていた所に座りながら言った。
「ご、ごめん、気にしないで……」
曖昧に笑ってごまかす。
「それにしても久しぶりだねぇ。私びっくりしちゃったよ!まさかこんな所でまた会えるとは思っていなかったんだもん!」
驚きを全身で表現しながら彼女は続けた。
「えっと……」
僕は反応に困る。
「もう、本当に覚えていないんだね……しょうがないなぁ、ハルくん?」
え!?なんで僕の名前を知ってるの?困惑する僕に、彼女はニヤニヤしながら言った。
「よぉし、これを見せたら流石にハルくんも思い出すだろうなぁ!へっへっへ〜!」
自信満々な様子で彼女はスカートのポケットに手を突っ込む。そして——
——ポケットから出された彼女の手には、鈴のついた赤色のリストバンドが一つ、握られていた。
「————!」
僕は彼女を食い入るように見つめた。そんな、まさか、でも、そ、それは……
「……り、りん、ちゃん?」
僕はおずおずとキオクノカケラに残る少女の名前を口にした。その途端、少女の顔が満面の笑みに染まった。
「ハルくん!思い出してくれたんだね!」
そう言って飛び跳ねる少女。
「ってことは……本当にりんちゃんなの?」
僕が問うと、少女は……りんちゃんは、コクリと頷いた。
「仰せの通りでございますですまするぅ〜」
「そ、そっか……」
……りんちゃん、だったのか。
「ねぇねぇ、フルネーム覚えてる?」
「な!?フ、フルネームデスカ?」
思わずカタコトになる僕。ごめんなさい、覚えていません。
「端沢鈴音だよ?鈴だから“りん”だよ?」
「ご、ごめん……」
「さっきから謝ってばっかり!せっかくなんだから、楽しく話そうよ!ね?」
りんちゃんは両手で僕の右手を握ると、上下に激しくブンブンと振った。
「そうだね……」
話といっても、何を話すのだろうか。というか、正直言って本当に名前の響きくらいしか覚えていないんだけど。とてもじゃないけど彼女にはいえないが。
「私ね、ここから少し離れた……家の近くのファミレスでアルバイトやってるんだよ?」
「へぇ、すごいじゃん」
「もっと褒めて〜」
ニコニコ笑顔で迫ってくるりんちゃん。
「え、えっと……すごいすごーい!」
そう言いながら、彼女の髪を遠慮がちに撫でてみた。ショートまで短くないが、肩につく程でもない。セミロングってやつかな?
「やったぁ!ハルくんが頭を撫で撫でしながら褒めてくれた!」
随分とご満悦のようである。
「バイト、忙しいの?」
「忙しい大変だけど、でもそれ以上に楽しいな。主に接客をしてるんだけど、たまに厨房の方に入らせてもらえて、色々勉強できるんだー」
充実しているみたいだ。
「ところで、ハルくんはなんで今日こんな所まで来たの?」
不思議そうにりんちゃんが尋ねてきた。
「えっと、ちょっと友達に連れてこられて、ね。僕の意思じゃないんだ」
「そうなんだ。だれだれ?どんな人?」
どんな人って言われてもなぁ……
僕が返答に困っていると、向こうの方から誰かが近づいてくる気配がした。あ、渦美さんがどうやら帰ってきたらしい。
「おかえり、渦美さん」
「…………」
渦美さんは、僕たちが座っているベンチから数メートル離れた所で立ち止まった。
「……渦美さん?」
今まで一度も見たことのない表情。目が大きく見開かれていた。
「……ど、どうして……」
震える声で、渦美さんは言った。
「……どうして、お前が、ここにいる」
一瞬僕に向けられた言葉かと思ったが、違う。渦美さんの視線の先には、僕の隣に座るりんちゃんに向けられていた。
「……どうしてって聞かれてもな〜?」
ケロリとした表情で受け応えをするりんちゃん。
「ねぇねぇハルくん、どこかに遊びに行こうよ、今日空いてる?」
そう言ってりんちゃんは腕を引っ張ってきた。
「いたた……痛いよ、りんちゃん。引っ張らないでよ」
「あ、相薙っ!」
「う、渦美さん、どうしたの!?」
渦美さんの声は、今まで聞いた中で一番大きかった。
僕はりんちゃんの手を振り切って、渦美さんの方へ駆けようと立ち上がった。しかし、途中で足がすくんでしまう。
「……何しに、来たの」
渦美さんの瞳が、<絶対零度>の瞳に豹変したのだ。そして<その>瞳は、りんちゃんを容赦なく貫く。
「ど、どうしたの?なんでそんな怖い顔をするの?」
りんちゃんの顔が恐怖で引きつる。
「ど、どうしちゃったのさ!二人とも、何があったの!?」
今まで体験した事のないような、険悪なムードに耐えられなくなって、僕は二人の間に割って入った。
「……相薙は関係ない。大丈夫」
渦美さんはりんちゃんを睨んだまま、突き放すような口調でポツリと言った。
「何しにって?……うーん、修行の旅とか?あはは!」
強がってか、ケラケラと笑うりんちゃん。
「……ふざけないで。何しに、来たの」
渦美さんが強い口調で問いただすと、りんちゃんの顔から笑顔が消えた。
「何しに、か……」
しばらく無表情に空を見上げて何かを考える。沈黙のあと、りんちゃんは言った。
「難しい質問だな。……そうだね、まぁ強いて言うなら————」
そして再び渦美さんの方を向いた時、彼女の顔には畏怖や怯えの感情のない、純粋な満面の笑みが溢れていた。<その>瞳が、容赦なく彼女を射抜いているというのに。
「————復讐……かな。お姉ちゃん?」
[絶対零度にデレはない 十 終]


