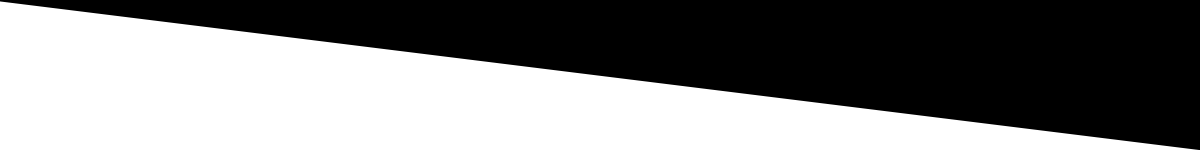
絶対零度にデレはない 二
- Absolute Zero No.2 -
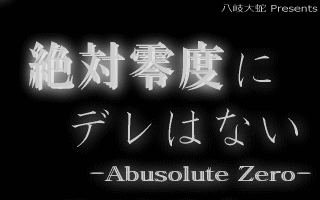
渦美さんが編入してきて四日が経過した。
この四日で特に変わった事は無かったけれど、強いて言うなら二つある。
一つ目はと進んでいた学園祭へ向けての準備についてだ。今日の終礼の時に行われるHRで、学園祭のクラス代表をくじで決める事になった。学園祭のクラス代表——もとい学園祭実行委員はクラスで二人ずつ選出されることになっており、実行委員になった人は設営や受付などの学園祭を運営するにあたっての重要なポストを、生徒会と協力してするのだ。場合によってはかなりハードな仕事を担当しなければならないこともあるので、忌避する生徒も少なくない。けど、僕個人の考えとしては、嫌とは思わない。積極的にやろうとは思わないけど、やりがいは有りそうだし、一回くらいは経験しても良いかもしれないと思う。
そしてもう一つは、渦美さんについてだ。編入してきた時から大体の人が予想していた通り、クラスの大半の人は渦美さんと距離をとっていたものの、特別嫌われているだとか、そういうのは無かった。しかし、先生からの伝言をおずおずと伝えに来たクラスメイトに対して<あの>瞳で睨みを効かして会話を拒絶したり、珍しく口を開いたかと思ったら、そこから発せられるのは「そう」だけという彼女の態度にクラスの皆も不快感を露にし始めた。皆が気の合う友達と机をくっつけ合って弁当を食べたりしている今も、彼女は一人で黙々と恐らく自分で作ったものと思われるサンドイッチを口に運んでいる。
そうそう、渦美さんにあだ名……ではないが、異名的なのが付いたんだった。本人は知らないかもしれないけど。<それ>は氷のように……いやそれ以上に冷たく、視線のあったものは恐怖で動けなくなる。さらに、他人の一切の干渉を拒絶する彼女の態度。これらを踏まえて色々な案が出されたのだが、つい先日決定した。<絶対零度>である。
うまい表現だとは思う。<絶対零度>の瞳……ね。的は得ているかもしれない。
「なぁ相薙。このクラスって学園祭で何するんだろうな」
近くにあった椅子を適当に持ってきて、僕の机で弁当を食べていた時雨が話を振ってきた。こいつも今日の午後に行われるくじについて考えていたのだろうか。
「喫茶店辺りで落ち着くんじゃないの?」
特に荒れているわけでもないし、接客にはそれほど困らないだろうし。
「俺はアレがして見たいんだけどな。ほら、最初に受付でスタンプカード的なのを配っておいてさ、配られた人は学校の色々な所に散らばっている特定の人を探して、あ、その特定の人ってのは腕章みたいな目印をつけてるから、で、カードが埋まったら受付に帰ってきてもらって、全部集めるのにかかった時間によってもらえる景品が決まるって奴」
「んんー、なるほど。それだったら準備もそこまで手間かからないし、景品しだいでは人も結構集まってくれそうだね」
そうだろ?と時雨は自慢気に笑う。
「景品も少しは貢献できると思うぜ。昔、駅前で配られてたポケットティッシュを集めまくっていて、殆ど使ってないから。家にあったダンボールに大量に保存されてる」
……微妙だな。
「あいつらも使われてナンボだからな。ずっとダンボールに詰め込まれているのも不本意だろうしね」
時雨は自己満足に浸ったっているのか、頷きながら言った。
リアクションに困った僕は、ミートボールを口に入れて、じっくりと咀嚼することにした。うん、美味い。
「……聞いてるか?」
不満そうな面持ちで時雨は聞いてきた。そんな彼に僕はふと思った事を唐突に言った。
「最近渦美さんと何か進展あったの?アプローチちゃんとしてる?」
「ぶはっ!」
「ちょ!僕の机にお茶が!うあぁぁ!教科書が濡れる!おい、どうにかしろよ!」
突如机上に訪れた惨事を指差しながら、僕は抗議の声を上げた。
「お前がいきなり変なこと言うからだろ!」
鞄からスポーツタオルを取って来た時雨は、それで机を拭きながら言った。
「いや、まぁ不意打ちって奴を……」
「なるほどな。俺はマンマとハメられてしまったってわけか」
時雨がニヤリと笑ってきたので、僕もノリでニヤリ笑い返す。
「で、結局どうなの?」
「…………」
悲愴感を漂わせながら俯く親友を見ていると、なんかもう、この話題は振らない方が良いのかもしれないなぁ、としみじみ思った。
教室にかけられた時計を見ると、休むことなくせっせと動いている長針と短針が、あと十分ほどで昼休みが終わる旨を告げていた。
「とっとと食べちゃおうか」
箸を動かすスピードを速めつつ、僕は言った。
「ん、そうかもな」
時雨も頷いて黙々と食べ始めた。
さて、昼休みが終わり、午後の授業も順調に消化されていき、いよいよ運命のHRの時間がやってきた。
「ホームルーム始めるぞ。全員、自分の席につきなさい」
そう言いながら入ってきた谷園先生の手には、丁寧に折りたたまれた多くの紙切れが入ったかごがあった。
「今から、今年の学園祭のクラス代表を決めるくじを行う。磯密、ちょっと前に出てきてくれないか」
「は、はい……」
先生から指名された磯密さんは、小首をかしげながらも席を立って教壇の上に立つ先生の横に並んだ。
「ここに一から三十三までの整数が書かれた紙がある。磯密が選んだ二枚の紙に書かれた番号を出席番号に持つ人が、今年の代表になってもらう」
「先生、なぜ私が選ぶのですか?」
磯密さんは不思議そうな顔で尋ねた。
「先生が選んでも良いんだが、色々と疑う奴も出てくるだろう。何らかの目印を事前につけておいて、ある特定の生徒を確実に選出できるように仕組んでいたのではないか、とかな。それなら、生徒が選んでくれた方がいらぬ憶測を呼ぶ可能性は低くなる。そこで、クラスを代表して委員長にくじを引いてもらうよう、今この場で頼んだのだ」
その意見には一切の異議なしだけど、自分が疑われる可能性を自ら思いつく先生って。「はい、分かりました」
先生の説明に納得したらしく、磯密さんも今度ははっきりと返事をした。
「じゃあ頼む」
そう言って先生は、くじの入ったかごを磯密さんに差し出した。
磯密さんは寸分もためらう事なく、二枚の紙をさっと取り、先生に差し出した。
「これにします」
先生は磯密さんから紙を受け取ると、クラスの空気の緊張が最高潮に達する。シーンと静まり返った教室に、ガサガサ、という先生が四つ折りにされた紙を広げる音が響く。
「えーっと、今年の代表を発表するぞ。公正な、くじの結果——」
公正な、を強調する先生。
「—— 一番と三十三番に決定した。」
僕は思わず苦笑した。確率的にはゼロではないけど、まさか本当に当たるとは思わなかった。
相薙という苗字は、小学校入学から今までの十一年間、一度も出席番号が一番でなかった事はないのだ。
……あれ?三十三番って確か——
「相薙と渦美か。よろしく頼むぞ」
編入してきたばかりだからか、“う”から始まるけど出席番号が最後尾の三十三番になっている渦美さんも選ばれていた。僕はちらりと渦美さんの方を窺ってみる。彼女は自分の名前が呼ばれた事を別段気にする素振りをすることもなく、鞄の中の整理をしていた。
「今日の放課後に早速一回目のミーティングがあるらしい。ホームルームが終わったら生徒会室の隣の小教室に行ってくれ」
そして先生からいくつか連絡事項が告げられ、HRは終わった。
挨拶を終えると教室の掃除当番に当たっている人達意外はぞろぞろと教室を後にし始める。僕は渦美さんの所へ向かった。渦美さんも生徒会室に行くのだから、思い切って一緒に行こうと誘ってみようと思ったからだ。
今思うと、初めて話しかけるな。僕は深呼吸を一つした後、渦美さんに声をかけた。
「えっと……渦美さん」
彼女からの反応はない。続けてみる。
「は、はじめまして。相薙です。同じ実行委員になりました。よろしく」
「……何か用?」
考えていたセリフを何とか噛まずに言えてひとまず安堵した僕に、彼女は開口一番冷たく言い放った。
「いや、生徒会室に一緒に行こうと誘おうと思って……」
やばい、気圧されてる。っていうか、いきなり一緒に行こうっていうのも、今冷静になって考えてみると、無茶すぎる気もする。
「……そう」
渦美さんは僕の方を見ずにそっけなく答える。
しばらくの沈黙。
「…………」
渦美さんは何も言わずに鞄を持って席を立ち、歩き始めた。僕もあわてて彼女の後を追おうとすると、彼女は振り返り、今日始めて目と目を合わせた。
一方的な拒絶の感情を持った<絶対零度>の瞳が射抜く。僕は反射的に固まった。まるで自分が石像になってしまったのかのようだった。
渦美さんは身を翻すと、そのまま振り返ることもなく教室を去っていってしまった。
取り残された僕は、<絶対零度>の瞳の影響か、若干ふらつく足取りで先生から指示された小教室へ、一人で向かうことにした。
教室を出る間際に僕の肩をポンポンと叩きながら「フられたか?まぁそう気を落とすなって」とか何とか言ってきた級友の鳩尾に右ストレートを容赦なく叩き込む。
先に小教室に着いたのは意外にも僕の方だった。僕の学校は海側と山側の二つの校舎に分かれていて、僕たちのクラスは海側の四階にあり、先生から行くように指示された小教室は、海側の校舎の一階にあるから、案外近いはずなんだけど。僕は前の黒板に貼られた座席表を見て、クラスごとに指定された席についた。
数分後、渦美さんはパックジュースを持って僕の前の席に来た。あぁ、食堂に行ってたから遅くなったのか。納得。
渦美さんが教室に入ってきた瞬間、小教室を半分程埋めていた、既着の生徒達からざわめきが起こる。おいおい、あんな奴内の学校にいたっけ?うわ、めっちゃ綺麗じゃん。あれ、お前知らないのかよ。この前横のクラスに編入生来てたじゃん。等々。
一瞬地の利を生かして渦美さんにもう一度話しかけてみようかと思ったが、さっきのような態度をとられることが目に見えていたので止めておく。傷つくだけだし。でも、自分の目の前にこんなに綺麗な人がいるのに黙っているのも男としてどうかと思う。
そんなことを考えてはみたものの、結局の所僕はチキンなようで、目の前にある長く艶やかな髪を黙って眺めること数分。大体の生徒は揃ったように思われるくらいに、教室が埋まってきたタイミングで、それまで腕を組みながら目を瞑っていた教室の一番入り口に近い席に座っていた男子生徒が突然立ち上がり、教壇に上がった。
その男子生徒は自分が生徒会長であることを告げ(まぁ言われずとも生徒会長の顔くらいは知っていたけど)、一緒に学園祭を盛り上げていこう、そのためには君たちの協力が不可欠だ、自分はまだまだ至らない部分も多いが精一杯努力するのでついてきて欲しい、等々の常套句を述べた。
生徒会長からの一連の挨拶が終わると、次にそれぞれのクラスが担当する係を決める事になった。どうやら仕事はクラス単位で決めるらしい。学園祭で使われる金券(現金は使えないのだ)を販売する係、受付、警備、設営など、結構な種類がある。
話のネタが出来たので、僕は思い切って渦美さんに話しかけてみた。
「渦美さんは、どれかやってみたい係ってある?」
「……特にない。受付以外なら良い」
前を向いたままそっけなく答えてきた。受付以外?
「何で受付以外なの?」
いや、たしかに渦美さん、接客とか苦手そうだけど。
「……べつに」
そう言って彼女はこちらを振り返った。
「……それが相薙の学校生活に関係があるというの?」
いや、あるよ。同じクラスの二人の実行委員は、同じ係につかなきゃいけないんだよ。
「いや、関係って……そういう意味で言ったんじゃないけどさ」
「……けど、何?」
「いや、だから」
「……だから、何?」
思わず土下座してスミマセンデシタと謝ってしまいたくなるレベルの冷たい態度に、半泣きになる。僕、失礼なこととか言ってないよね?
「……あなたには関係ない」
何も言えずにただ口をパクパクしていた僕に渦美さんはそう言うと、くるりと前を向いてしまった。
トドメの一撃を食らって撃沈した僕は思わず机に突っ伏した。
さて、二十分後。
結果から言うと、僕達はステージ設営にあたる事になった。軽音楽部の演奏、ダンス部の演技、有志による漫才など、数多くの催し物が、体育館に作られる特別ステージで毎年行われる。そのステージの設営をするのが主な仕事の内容だ。そのままだけど。
事前の準備は大変だが、警備などとは違って学園祭当日は自由な時間が多いので、結構おいしい仕事かもしれない。
僕達の他にも設営係になったクラスはあった。三年生が二クラス四人、二年生が二クラス四人、一年生が三クラス三人。……あ、そういえば一年生は一クラスにつき実行委員は一人だけだっけ?
「えと、一年C組の斜向紗姫と言います。よろしくはじめましてです」
生徒会長の解散宣言にしたがってぞろぞろと小教室から出て行く人の波に乗って、小教室を後にしようと席を立った僕と渦美さんの前に現れた一人の女の子は、ペコリと頭を下げながら言った。あ、この子はたしか……
「あぁ、同じ設営で後輩の子か。どうもはじめまして、相薙です」
とりあえず、よろしくはじめましてです、という前代見聞の挨拶には何も触れずに自己紹介をすることにした。
渦美さんはじーっと彼女を見ている。
「相薙先輩ですか。よろしくお願いしますです」
そう言って無邪気にニコニコとはにかむ斜向さん。
「えっと……」
彼女はちらりと渦美さんの方を見ながら言い淀む。
「……渦美怜香」
ぼそりと、しかし良く透った澄んだ声で渦美さんは言った。
「あ、えと、渦美先輩ですね。よろしくお願いします」
またペコリとお辞儀をした、頭を下げるたびにサイドテールの髪が揺れる。
「渦美さんどうしたの?そんなに斜向さんのことじっと見て」
僕は、ニコニコ笑顔を絶やさない斜向さんと、全くの無表情の渦美さんを交互に見ながら尋ねた。
「……べつに。とくに何もない」
「そ、そう。なら良いけど」
「わ、私の頭に何かついているのですか?」
不安そうな面持ちで、頭を触りながら僕に問うてくる斜向さん。不安というか、怯えとも取れるものが表情には表れている。
「そこは顔に何かついているか聞く所だね。……いや、そんな事はどうでも良いか。べつに何も付いてないから大丈夫だよ」
「そ、そうですか。なら良かったです。えっと、それじゃあお疲れさまでした!これから一ヶ月と少し、よろしくお願いします!」
斜向さんはパッと笑顔になった。
「ん、お疲れ様」
「…………」
渦美さんの視線から逃げるかように、わたわたと走り去って行った斜向さんの後姿を見送った後、渦美さんは僕に向かっていった。
「……昔の、知り合い?」
「違う、初対面だよ」
はじめましてです、って言ってたじゃん。
「……そう」
会話が途切れる。しばらくすると渦美さんは一人でとっとと扉から廊下に出て行ってしまった。一人取り残される僕。
ここにいても何もする事はないし、僕も小教室をあとにすることにした。
[絶対零度にデレはない 二 終]


