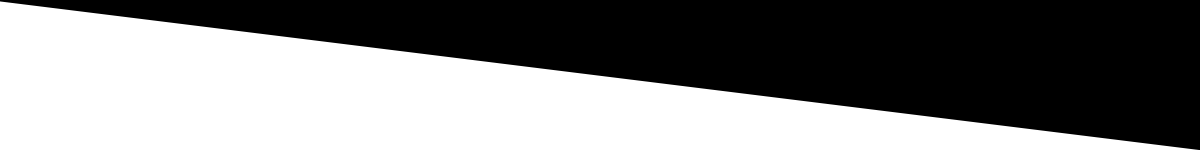
絶対零度にデレはない 三
- Absolute Zero No.3 -
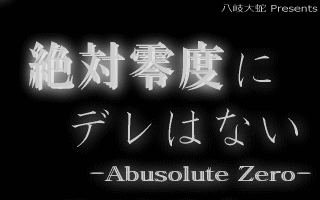
日曜日の朝。僕はリビングで朝食を摂っていた。
「やっぱりハルの作ったご飯は最高だね、うんうん」
そう言いながらテーブルを挟んで僕と真向かいに座りつつ、出し巻き卵を頬張っているこの人は、僕の姉の優菜姉さんだ。
「いやいやそんな。大した事ないよ」
「おや、謙遜ですかぁ。ハルも大人になったねっ」
ニコニコしながら姉さんは言った。
優菜姉さんは僕の四つ上で、大学二年だ。両親共に働いているので(父さんは単身赴任だ)家では姉さんと二人になる事が多い。ハルとは僕の下の名前の利晴から来ていて、小さい頃からこう呼ばれていた。
「あ、そうだ。実はこの前のHRでさ……」
僕は出し巻き卵から話題を変えるべく、この前のHRでの出来事を話すことにした。
「ん?何かあったの?」
金曜日のHRで学園祭の実行委員を決めるくじをしたこと、そして自分と渦美さんがそれになったこと、色々ある係の中で設営を担当する事になったこと、などを話した。
「へぇ……その渦美さんってどんな子なの?最近編入してきたんじゃなかったっけ?」
姉さんはお箸を置いて聞いてきた。僕は言葉に詰まる。
「えっと、そうだね……」
「どうしたの?」
「んと、あまり話してもらえなくて……」
「嫌われちゃったの?」
苦笑しながら言う僕を見て、姉さんは首を傾げた。
「いや、嫌われるというか、最初から拒絶されてるというか、どの人にも同じよな態度をとってるんだけどね」
「ふむふむ。その子って、口癖とかある?」
「な、何だよいきなり」
姉さんの考えが読めない。
「ちょっと気になってね」
僕はテーブルに並べられた皿をじっと見ながら考えた。
「えっと……大抵『そう』とか、短い言葉で終わるからなぁ。口癖以前の問題だと思うけど」
僕が顔を上げると、姉さんはニヤニヤしていた。それはもう気持ち悪いくらいに。
「え?僕なんか変な事言った?」
「ほっほーう、クーデレですか、そうですかぁ……ハルも美味しいトコロを持ってきたじゃない。やるねぇ、うんうん」
「は、はぁ?」
呆気にとられる僕。い、いきなり何を言い出すんだ姉さん。
「しか〇.二%の確立の壁を超えて仲良く実行委員かぁ。フラグたったも同然だね」
姉さんは一人で頷きながら、満足気な笑みを浮かべた。
「……姉さん、意味が分からないんだけど」
「え?だってほら、数Aの範囲だよ?三十三人のクラスから、特定の二人が委員に選ばれる確率は……」
「そっちじゃなくて!」
いきなり数学の授業を始めようとした姉さんを慌てて止める僕。
「その、クーデレとか何とか」
「なるほど。よし、じゃあ私が可愛くて奥手で儚くて童貞で初々しくて可愛いハルの為に一から説明してあげるね」
「『可愛くて』がかぶってるよ……ってなんか四番目に聞き捨てならない言葉が入ってた気がするけど、僕の気のせいかな!」
「まず、クーデレっていうのは代表的な萌え属性の一つとして挙げられてね」
……無視された。
しかし、この流れは非常にまずい。過去の経験的に僕の直感がそう告げている。
姉さんの口から『萌え属性』という単語が出てきて話が短くまとまった事など一度もない。平均して二十分は語り続ける。
「クーデレって一口に言っても幾つかのパターンが存在するんだけど、まぁ共通して言える事は、ハルがさっき言ってたみたいに『そう』とか、『だから』とかそっけない言葉が多いのよね。クーデレキャラの序盤って」
姉さんはアニメとかマンガとかが好きで、ちょっとした用事があって何度か姉さんの部屋に入ったことがあるけど、凄かった。どこであれだけの量のグッズやら何やらを揃えるのだろうか?僕はあまりよく分からないが、級友に一回姉さんの部屋に転がっていた諸々の物について、僕の持ちうる限りの語彙を使って説明してみた所「うわぁ、スゲェなお前の姉ちゃん。萌えやら燃えやら百合やらBLやら多岐に渡り過ぎだろ」とか言われた。正直よく分からなかったので、自分から聞いておいてなんだが、気にしないことにした。
「一般的な攻略方法としてはね……」
「いや、さすがにゲームと一緒にしちゃまずいと思うんだけど」
「違うよ、ハル。近年の目覚しい研究で、次元の狭間って意外と曖昧なものだと信じられるようになってきたんだよ」
「勝手に有りもしない研究作らないでね。しかも証明されたんじゃなくて、信じられるようになっただけなんだ」
「まぁまぁ細かいことは気にしちゃダメ!」
「姉さんがアバウト過ぎなんだよっ」
「でも、ハルにはちょっとレベル高いなぁ」
うーん、と米神を押さえる姉さん。またこの人は、いきなり何を言い出すんだ。
「せめてツンデレだったらなぁ……王道中の王道だし、もうデレる所までの道筋は大抵解明されているんだけど……」
よし、決めた。放っておこう。
「ねぇハル。その渦美さんって子の特徴をもう少し教えてよ」
「(モグモグ)」
「ちょっと参考にしたいからさ。ね?」
「(モグモグ)」
「今夜一緒にお風呂入ってあげるからさ」
「(モグモ……)ゲホ!ゴホッ!」
く、くそ!不覚にも噎せてしまった!
「真面目な話、どんな子か知りたいのは事実かな。話を聞いてる限りじゃ、孤立してるんじゃないの?まぁ弟の級友について首突っ込むのも行き過ぎかとは思うけどさ」
姉さんが少し真剣な顔になった。
「そ、そうだね。確かにクラスではいつも一人だよ。でも、本人が嫌がってるんだし、良いんじゃない?」
「良いわけないよ」
珍しく姉さんの口調が厳しくなった。
「クーデレキャラは……いや、クーデレに限らず、自分からアプローチに行かないと、先には絶対に進めないよ?」
姉さん、頼むから真剣な顔でそんな事言わないで。リアクションに困るから。
「それに、同じ実行委員でしょ?親友とまでは行かなくても、ある程度の関係にはなっとかないと、色々不便でしょ?コミュニケーションの面でさ」
「それは、そうだけど……」
「基本は、というか一番初めにすべき事は、とにかく話しかけるの。仲良くなるためにはこちらからアプローチしないと。これ、ゲームでも現実でも使える理論だからね」
そう言って姉さんは優しく微笑んだ。
「なんか……凄くタメになるような、ならないような……」
良いことを言ってくれてるんだけど、所々に必ず余計な情報が入るのは勘弁願いたい。
「よし、じゃあさっさと朝ごはんを食べちゃおうか!」
「ん?何か今日用事でもあったっけ?」
「ハルにしっかりと勉強してもらわなくっちゃね。敵を知らずして何とかって言うし」
「……姉さんの笑顔を見てたら何故か鳥肌がたってきたよ」
「リアルギャルゲはコンティニューが効かないからね。心してかからないと」
そう言って、箸を持ちながら右手で拳をギュッと握る姉さん。
「だからゲームじゃないってば……」
僕の声は、きっと姉さんには届いていないのだろう。
そして朝食後、僕は一時間以上クーデレ属性とやらについての姉さんからの熱い講義を受けることになるんだけど、これはまた別のお話。
次の日、僕は朝の教室で早速昨日姉さんから教わった事を実践しようとしていた。とはいっても、とにかくこちらから話しかけるだけだけど。
僕は右手にこの前の委員会でもらったプリントを持って、自分の席で黙々と読書をしている渦美さんに話しかけてみた。
「おはよう、渦美さん」
渦美さんは本を読むのを止めた。本は開いたままだったし、視線はまだ本に向かったままだけど、目の動きが止まったのだ。
「設営の事で話があるんだけど……ちょっといいかな?」
渦美さんから返事はない。でもかまわず続ける。
「ここの入り口付近についてなんだけどさ、ここが——」
僕が言い終えると、彼女は本を閉じて机におき、筆箱からシャーペンを取り出した。
「……相薙の意見には賛成できない」
「と言うと?」
「……その考えは、一時的な混雑は解消できる。でも、根本的な解決には至らない」
彼女はプリントに描かれた、体育館に設営される予定であるステージの見取り図の上に諸々の情報を書き込みながら淡々と言った。
「……浅はかな考え」
そ、そんな風にボソッと言われると結構傷つくんですけど。
「分かった。じゃあまた別の案を考えてくるよ」
「……そう」
渦美さんはシャーペンを筆箱にしまうと、もう用は無いだろうと言わんばかりに読書を再開した。僕はすごすごと退散する。
次の日。昼休み。
「渦美さんって、何か部活に入る予定ってあるの?」
授業であと十数分ほどあり、ほとんどの生徒は昼食を終え自由な時間を過ごしている。自分の席でボーっとしていた渦美さんに話しかけてみた。
「ない」
即答。やばい、ないと言われちゃ会話が続かない。
「ち、ちなみに僕も何も入ってないんだけどね……」
中高通じて帰宅部の僕である。
「……だから?」
「いや、僕も人の事言えないんだけどね。はははは」
「……そう」
「部活とか入った方が学校が楽しくなるぜ、って時雨に言われてね。そう思う?」
「……べつに」
渦美さんがこちらを向いた。<絶対零度>の異名をとる視線が僕を射抜いた。一瞬背筋が凍る。
「……あなたには関係ない」
そう言い放つと、渦美さんは席を立ってどこかへ行ってしまった。
次の日。放課後に実行委員が招集された。その後廊下にて。
「どうしたの?難しい顔して」
廊下を歩きながら、何かを考え込んでいるらしい渦美さんがいた。
「……べつに」
そっけなく返してくるが、絶対何かあると思う。
「委員について?」
「……べつに」
「設営について?」
「…………」
その無言は、肯定のサインと受け取った。
「斜向さんのこと?」
しばらく無反応だったが、やがてコクリと頷いた。
「……わからない」
渦美さんは立ち止まって呟いた。
「……初対面の人にあれだけ笑顔になれる理由がわからない」
一回目の召集で、小教室を出ようとした時の事だろうか?
「そっか……」
「……相薙は、どう思う?」
「ぼ、僕的には印象良かったけど……」
「そう」
僕は聞いてみる。
「笑顔って……いいと思うけど、渦美さんはそう思わない?」
「……べつに。良いとも、悪いとも」
渦美さんは淡々と答える。
「まぁ、人それぞれ考え方はあるもんね」
会話が途切れる。なんだかんだで教室まで一緒だったけど、この日はこれ以上渦美さんの口が開くことはもう無かった。
その日の夕食はカレーだった。家に帰ると姉さんが作ってくれていた。
「ん、美味しい。前に作ってくれた時よりもレベル上がってるね」
素直な感想が口から出た。それを聞いた姉さんの顔が綻ぶ。
「ありがと。私も弟に負けてられないしね。逆襲ってやつだよ、うん」
姉さん、逆襲とは言わないよ。
「そうだ、最近どうなのよ、渦美さんって子とは」
「あ、うん。えっとね……」
僕はここ三日間の出来事を話した。姉さんはスプーンを口に咥えながら(行儀悪いけどここでは見過ごしておく)僕の話に真剣に耳を傾けてくれた。
「……ほほーう。やるね」
僕の話を聞き終えて、姉さんは開口一番ニヤリと笑いながら言った。
「えっ?」
「いやー私の予想ではもう少してこずるかと思ってたんだけどね」
姉さんは続ける。
「最近ツンデレとかクーデレ系のキャラのデレるまでの時間が、短くなっている傾向が指摘されているけど、その影響かな?」
「だからゲームと一緒にしないってば!」
「ハルも大人になったね。こりゃあ激ツンの幼馴染がいても、無駄なく最速の時間でデレさせるレベルになりつつあるね」
「『大人になったね』の基準がおかしいよ!あと僕に幼馴染とかいないから!」
「ふぉえっ?」
姉さんはポカンとして変な声をあげた。
「ど、どうしたのさ」
「……いや、なんでもないよ。でもこれは難しいね……うーん」
攻略、とかルート、とかブツブツ言いながら考え込み始めた姉さん。あぁ、こりゃもう駄目だ。こういう時の姉さんは、何を言っても右から左で聞こえていない。さっきの姉さんがあげた変な声の所以を問いただそうかと思ったが、無駄だと思ったので止めておく。
僕はカレーを口に運ぶ。きちんと香辛料が効いていて辛味がある中に、まろやかで優しい味が口に広がった。不思議だ。何を使っているんだろう。
「それはね、愛情と言う名のスパイスが効いているからだよ」
どうやら、姉さんがこちらの世界に戻ってきた。今日は意外と早かったな。
「僕の心を読んだ上でのその発言は、素直に凄いと思うけど、よくそんな寒いセリフが言えるね!?いや、愛情はすごく嬉しいけど!」
「ハルの表情を見ていると、何を考えてるのかお見通しなのです」
そう言って姉さんは優しく微笑んだ。思わずこちらもつられて表情が緩んでしまう。
姉さんは若干変わった人だけど、本当に温かい人だと思う。中学に上がって時くらいから、両親の顔を見る時間よりも、姉さんと一緒に過ごす時間の方が長かったせいか、四つ違いだけど母親のように感じられる。
「ねぇ、ハル」
「ん?なに、姉さん」
「ハルは素直な子だからね。まっすぐに自分の気持ちを伝えたら、絶対に受け入れてもらえると思うよ?」
姉さんはゆっくりと、諭すような口調で優しく言った。
僕はカレーを口に入れて、姉さんの言葉と一緒に咀嚼した。
やっぱり、姉さんの作ってくれたカレーは最高だった。
[絶対零度にデレはない 三 終]


