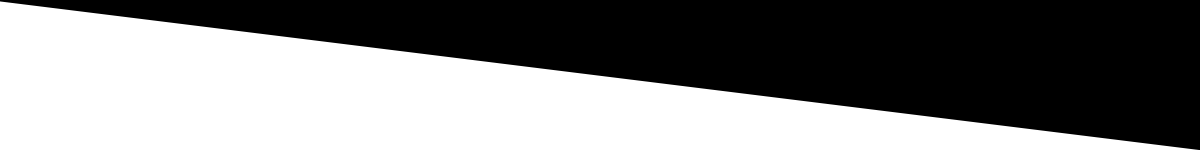
絶対零度にデレはない 四
- Absolute Zero No.4 -
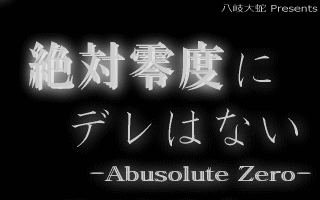
ある日の昼休み、その日はたまたま弁当じゃなかった僕が、食堂でラーメンでも食べようかなと考えながらフラフラと教室を出た時のこと、後ろから比較的聞きなれた声が僕のことを呼び止めた。
「相薙、ちょっと良い?」
磯密さんだ。一体何の用だろう?
「どうしたの?」
「えっと、まずはコレを渡さなきゃ。委員会が開かれる日時が書かれた紙ね」
そう言って、磯密さんは手に持っていた一枚の紙を僕に差し出した。
「あぁ、ありがとう」
僕はありがたく受け取った。たしかに、これがないと困るよね。
「でも、何であの時配らなかったんだろ?」「生徒会長の不手際らしいわよ。まぁミスは誰にでもあることだから咎める気はないけどね。会長が自ら、委員長の私のところに渡しに来たのよ。たしか朝だったかな」
なるほど。委員は基本的にクラス単位で召集されているわけだから、各クラスの委員長に頭を下げて預けておけば、必ず委員の方には渡されるだろう。
「私、あの人どうも苦手だなぁ」
そう言いながら磯密さんはため息をつく。
「え?どうして?」
「だって、固すぎるもん。何というか、台詞の一つ一つが計算され尽くされているというか、べつに利害得失に捕らわれてそうってわけじゃないけど、話しててつまらないよ」
固すぎる、というのは分からなくもないかもしれない。
「まぁ『分かりました、わざわざご足労様です』って笑顔で言っといたけどね」
やっぱり女子って怖ぇ。
「……何か言いたいことでもあるのかな?」
笑顔で尋ねてくる磯密さん。
「な、なんでもないです!はい!」
「……そうそう、あともう一つ」
磯密さんは真顔になった。
「渦美のことでちょっとね。最近、積極的にアプローチを続けている相薙なら分かるかなと思って聞くんだけど、」
「べつに積極的にアプローチしてるわけじゃないんだけどね」
僕は間髪をいれずに否定しておく。
「渦美と話すってどんな感じなの?やっぱり普通とはちょっと違う?」
「うーん……会話になってるかどうか少し怪しい所もあるけどね。向こうからの返事はかなり淡白なものが多いし、渦美さん的に踏み込んで欲しくない領域があるみたいで、もしそこに踏み込んだら『あなたには関係ない』って一蹴される」
「委員長って立場を利用するわけじゃないけど、少しは仲良くなれるかなーって思ったんだけどね。取り付く島も無いのよ。一応普通に話せるようにはなりたいんだけど……」
うーんと考え込む磯密さん。彼女なりに結構真剣に悩んでいるのだろう。
「…………」
僕は何か言おうかと口を開きかけたが、止めた。このシュチュエーションで、僕が言うべき台詞や逆に言ってはいけない台詞が分からなかった。
「あんなに冷たい態度で接さなくても良いのにね。なんか凹むなぁ」
「そ、そうだね……」
「でも、相薙は例外みたいだね。積極的なアプローチが実を結んだのか、」
「だから違うからね」
もはやゲーム感覚で突っ込む僕。例えるなら、もぐら叩きとか、そんな感じ。
「結構仲良いんじゃない?うんうん」
まずいなぁ……クラスのみんなからも誤解されているのかなぁ。間違っても「姉さんからの指南で」とか言ったら、今度はシスコンの汚名まで着せられるかもしれないし、下手な事は言えない状態だよなぁ。
「相薙って渦美のマネージャーとか似合いそうだよね」
満足気に頷いていた磯密さんが、突然そんなことを言う。
「どこからそんな発想が出るのさ」
「渦美、この前の体育で意外と運動神経は良かったから、そう遠くは無いかもよ?」
「何に!?何に遠くないの!?」
「クールで冷徹なキャラの渦美についている相薙は、周りの人から『マネージャーの人、可哀相だな。裏ではこき使われているんだろうなぁ』って同情されていてね」
「僕、こき使われている設定なんだ!」
「それを見かねたコーチが相薙に『すまねぇな。あいつはどうも人から干渉されるのを嫌うらしく、マネージャーのお前にまで辛く当たっているかも知れねぇ。一人の力では一流のアスリートにはなれねぇって、あいつはあいつなりに分かっているようだが……。しかし、あいつと上手くやっていけるのは、お前だけなんだよ。俺ですら、まともに話してもらえねぇ。頼む、あいつの傍でこれからもずっとサポートしてやってくれ』って言うの」
「ねぇ、これ何の物語?今ここで話す意味ってあるの?」
「そしたらね、相薙はコーチにこう返すの。『ふっ、コーチ。心配には及びませんよ。僕は彼女のことを愛しています。惚れているのです。しかし、世界を目指すトップアスリートを目指す彼女の道を、たった一人のマネージャーの私情で邪魔する気はありません。彼女の冷徹さやクールさは、僕の頭を冷やしてくれるのに、ちょうど良いのです』」
「僕、そんな『ふっ』とか言いながら笑うキャラじゃないよ!?あと、別にカッコイイワケでもなく、かといって面白いわけでもなく、チョイスとしては超微妙な台詞だよ!?」
「いーじゃん、相薙だし」
「ひでぇ!」
「……あれ?何の話してたんだっけ?」
「自分が勝手に始めた話に付き合わせておいて、きょとんとした顔をしながら、首を傾げつつ可愛く聞いてくるなよ!」
返せ!僕の昼休みを返せ!くそ、多分もう食堂の席はほぼ満席だろうな……
「いや、ボケているわけでもないのに、突っ込む相薙が面白くてね、つい」
てへっ、と舌を出す磯密さん。
「…………」
完璧にしょぼくれて黙り込んだ僕の背中をバシバシ叩きながら、磯密さんは笑う。
「相薙、食堂のつもりだったの?」
「そうだけど……どこかの誰かさんのせいで多分もう満席だよ。昼休みが終わる十五分前くらいにいったら、もう座れるだろうけど、食べられるものは限られているだろうし」
「うーん……ちょっと待ってて」
磯密さんはそう言い残して、僕の視界から消える。十数秒後、磯密さんは袋を持って帰ってきた。購買の袋かな?
「そういうことなら、これを売ったげる」
そう言って磯密さんは手に持っていたビニール袋からサンドイッチを取り出す。
「え?どういうこと?」
「この百八十円のサンドイッチを百五十円で売ってあげるよ。で、食堂が空いた頃に簡単なものでも食べれば良いんじゃない?さすがに少しは私の責任だし、放っておけないし」
いや、百パーセント磯密さんのせいだし。
「ありがとう。でも、良いの?」
「べつにかまわないよ。他にもあるから」
「そ、そうなんだ……」
「あはは、さっきまで凹んでいたのに、すぐに機嫌直ったね」
「直ってないよ!っていうか、凹ましてた自覚あったのかよ!」
いきなり目の前にサンドイッチが差し出されたものだから、虚を突かれてしまっていたが、間違いなくついさっきまではイライラしていた。くそ、餌につられた気分だよ。
「どうする?買う?」
「あ、はい、いただきます」
僕がそう言うと、磯密さんは手のひらを差し出してきた。ポケットから財布を取り出して、百円玉と五十円玉を一枚ずつその上にのせる。
「まいど〜」
彼女は僕にハムカツタマゴサンドを手渡すと、教室の隅の方で机を寄せながらかたまっていた、数人の女子が集うグループの輪の中に溶け込んでいった。
そんな彼女をみながら、人望ある人はすげぇなぁ自然と輪の中に入っていったよ、なんて思いながら、僕はハムカツタマゴサンドを頬張るべく自分の席に向かった。
放課後、委員が召集された。場所は実際にステージを設営することになる体育館。いよいよ本格的な活動が始まるのだ。ステージの照明やBGMなども設営が担当することになっているので、本番が近くなれば具体的にその辺も議論されるのだろう。
学園祭実行委員の生徒用マニュアルのようなものが全員に配られ、これからの全体の大まかな予定の流れについての説明が、設営の統率にあたる体育の山畑先生からされた。
「結構大がかりな作業だな……」
僕はマニュアルを見ながら思わず呟く。そこに書かれたものを見る限り、やはり特設ステージと言うだけあって、外部から色々な物を借りてきて装飾するらしい。
一通り説明が終わると、先生は今日のクラスごとにそれぞれの役割を口頭で与えると、しばらくしたらまた戻って来る旨を伝えて体育館を出て行った。山畑先生は野球部の副顧問でもあるから、そちらの方にも少しは顔を出しておきたいのかもしれない。
「渦美さん」
僕たち二年B組は客席の配置、出入り口や係生徒の通路等の配置を考えておけ、と言う事だった。早速、すぐ近くに座っていた渦美さんの所に行って話し合うことにする。
「……何?」
「どうしようか?早いとこ考えてしまった方が良いのは分かっているんだけど……」
「……難しい」
マニュアルを凝視しながらポツリと渦美さんは言った。
「だよね。いきなり考えとけっていうのは、かなり酷だと思う」
「……とりあえず、客席の配置と出入り口の場所や個数は重要」
「客席はいくつ用意するのかな?」
「……分からない。どうやって置くかで変わるから」
渦美さんはここで一旦言葉を区切る。
「……でも、マニュアルによると、用意できる椅子の数は限られている」
「立ち見席も、ありかもしれないね」
「……しれない」
えっと、これは肯定の意思表示と取っていいのかな?
「……整理券についても考える必要がある」
「か、考えなきゃいけない事が山積みだね」
僕の言葉に渦美さんはコクリと頷いた。
「……山積み」
「とりあえず、やれる事からやっておいた方が良いかもね」
「…………」
ページをめくりながら、マニュアルを無言で睨むこと数十秒。渦美さんはスッと顔を上げ、僕の方を向き、こう言った。
「……誤字脱字を三箇所見つけた」
てっきり“やれる事”を探しているのだと思っていた僕は、思わずずっこける。
「……どうしたの」
大仰なリアクションを以って、いきなりその場に倒れた僕を見て、怪訝そうな顔をしながら渦美さんが言った。
「い、いや、なんでもない」
「……そう」
僕が苦笑しながらそういうと、渦美さんは僕から興味を失ったように目をそらし、フラリとどこかへ行ってしまった。ヤベ、変に思われてしまったかも。
この日の集まりだが、あの後しばらくすると先生が帰ってきて、「今日はもう解散で良い」とのたまったことでお開きになった。多くの生徒が、おいおい結局マニュアル配っただけじゃないかクソ山畑、と文句を垂らしながら体育館を出る中、僕もその波に乗って帰路につくことにした。渦美さんは二番目か三番目くらいに体育館を出て行ってしまっている。急ぎの用でもあったのだろうか?
「相薙先輩、お疲れ様でしたです」
体育館を出ると、バッタリ斜向さんと遭遇した。
「あ、お疲れ様」
彼女の向日葵が咲いたような笑顔を目の前にすると、僕の表情も自然とゆるんだ。
「設営って大変なのですね……マニュアルを見てびっくりしちゃったです」
そう言って斜向さんは肩をすくめる。
「たしかに、マニュアルを見る限りきつそうだよね。でも、学園祭当日はフリーって言っても過言ではないから、当日の警備にあたる係よりはマシって考えも出来るよね」
「ポジティブシンキングなのですね!ネイティブシンキングはだめ、と」
なるほど、なるほど、と何度も頷きながら斜向さんは満足そうに笑った。
「いや、べつに僕は母国や出身地の言語の考え方に対して、否定的な意見を持っているわけじゃないからね…………無理だよ!このボケに対してツッコミ入れるの難しいよ!」
「ふぇ?どうされたのですか?」
「本人は素で言ってるらしいし!」
すると斜向さんは小首を傾げながら、
「もしかして、ポジティブシンキングではないのですか?」
と尋ねてきた。
「いや、そうじゃないよ」
「ポジティブではないのですか!?」
「そっちを否定したんじゃないよ!」
「うぅ……ごめんなさいです……」
僕が思わず大声をあげると、斜向さんは俯きながら肩を振るわせ始めた。
「あ、その、ちょ、待ってごめん僕が悪かった!」
今僕たちがいるのは体育館前。部活等で放課後残っている生徒が比較的多く通ることのある場所だ。シュチュエーション的にまずいと反射的に感じた。
「その、私、無意識のうちに先輩に対して失礼な事を言っていたのかもしれません。ごめんなさいです……だって、先輩怒っちゃいましたもんね……」
「いや、僕怒ってないよ?ちょっと大きい声出しちゃったのは、勢いと言うか、べつに怒りから来たものじゃないからさ。ビックリさせちゃったみたいだね。ごめん」
傍から見れば「体育館前で後輩の女子を泣かしている先輩男子」というこの状況から、とにかく僕は脱却したかった。
「そ、そうなのですか?」
僕が必死に紡いだ言葉が効いたのか、斜向さんは恐る恐るといった感じに顔を上げ、僕の様子を窺ってきた。
「うん、そうそう」
おずおずとした仕草×若干潤んだ瞳×上目遣い=最強
脳裏に一閃した世界一美しい方程式を必死に頭の隅に追いやりながら、僕は取り繕うような笑顔で、さっきの彼女のように何度も頷いた。
「よ、良かったです……先輩に嫌われちゃったかと思いました……」
目じりを拭いながら安堵の表情を浮かべる斜向さんに、僕は言った。
「いや、全然そんな事ないから。ごめんね、これからあまり大声出さないように気をつけることにするよ」
「えっと、渦美先輩はどちらに?」
ふと思い出したように斜向さんは言った。
「渦美さんなら先に帰っちゃったよ」
「そ、そうでしたか……」
虚を突かれたのか、斜向さんは一瞬ポカンとした。
「渦美先輩にも、ご挨拶したかったんですけどね……また次の委員会のときにします。そ れでは、お先に失礼しますね」
「うん、じゃあまたね」
満面の笑みでペコリとお辞儀をし、ダッと駆けていった斜向さんの後姿を、僕は手を振って見送った。
[絶対零度にデレはない 四 終]


