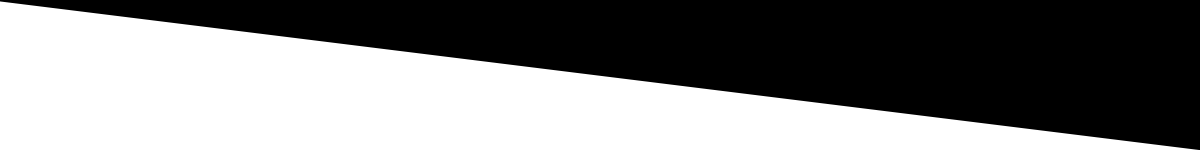
絶対零度にデレはない 五
- Absolute Zero No.5 -
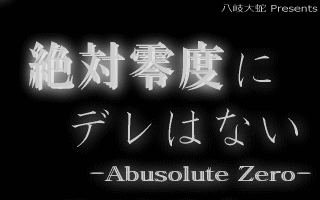
山畑先生からマニュアルを受け取ってから土日を挟んで一週間が過ぎた。
あれから僕たちは、二日に一回のペースで一時間ほど体育館に駆り出されている。比較的ハイペースに仕事を進めているおかげか、最初はどうなる事かと不安になっていた設営の仕事も、だいぶメドが立ってきた。客席の配置や席数、出入り口の場所なども他の係の人も交えて相談し合い、この前の委員会で何とか確定案を捻り出す所まで漕ぎつけることが出来た。話し合いには渦美さんは勿論、斜向さんも積極的に参加してくれて、すごく助かったし、親睦を深める事が出来たと思う。次の委員会では、山畑先生に確定案を一度見せてみて反応をうかがう予定である。
さて、今日は特にする事もないし早く家に帰って本でも読もうかな、なんて思っていた放課後。教室から出ようとしていた所を磯密さんに呼び止められた。
「相薙〜」
「ん?どうしたの?」
振り返って磯密さんと向かい合う。
「委員の方、最近どんな感じ?」
「あぁ、結構順調だよ」
「そっか。なら良かった」
そう言って磯密さんは安堵の表情を浮かべる。
「渦美ともうまくいってるみたいだしね」
「そうかな?」
まだ態度はだいぶ冷たいけど。
「私が見ている限りだと、まともにコミュニケーション取れてるの相薙だけだよ」
「ま、まぁね」
「やっぱり学園祭だしさ、クラスで一致団結したいからさ、相薙に頼みたいのよ」
「……何を?」
話の流れ的に大体予想はつくけど。
「渦美を上手いことクラスの輪に入れて欲しいなぁってね」
「それは……渦美さん次第なんじゃない?クラスに馴染めていないのも、原因の根本は渦美さん自身が僕達との関わりを拒絶している事にあるんだし」
「でも相薙とは話してるじゃない」
「それは、同じ実行委員だからとか?」
「違うと思うな。たとえば、仮に私と渦美とで実行委員になっていたとしても、私が話しかけたら渦美は<絶対零度>……だっけ?その瞳で私を拒絶すると思う」
「それは分かんないだろ」
「まぁ渦美がまともに会話しているのを見たことがあるのは相薙だけっていうのは、ゆるぎない事実なんだけどね」
「はぁ……」
「だからさ、何とか説得してくれないかな?クラスの皆も本当は仲良くなりたいと思うんだ。もちろん私もね。渦美が心を開いてくれたらクラスももっと団結できて、もっと学園祭を楽しめると思うし……」
「そ、そうだね」
「だから、ダメ元でも良いから何か言ってみてくれない?お願いっ」
クラスを代表する委員長にお願いされてはこちらも断りづらい。
「……分かった。頑張ってみるよ」
僕がそう答えると、磯密さんの表情がパッと明るくなった。
「あ、ところでさ。相薙って渦美とメアド交換していたりするの?」
「してないけど、なんで?」
「へぇ意外。てっきり家に帰っても仲睦まじくメールとかしてるのかと思ってた」
「なんか……誤解してるよ」
僕はため息をつきながら言った。
「僕たち、そんな仲の良い関係じゃないからね」
「でも、相薙は渦美のことが好きなんじゃないの?」
一瞬言葉に詰まる。否定は出来ない。
っていうか、磯密さん、サラッと自然な流れでそんな事聞いてこないでよ。
「好きか嫌いかで聞かれたら前者だろうけど……嫌いになる理由は無いしね」
磯密さんは少し考えてから言った。
「よし、じゃあね。渦美って綺麗だよね」
「うん」
そりゃあ百パーセント肯定だ。
「綺麗な人って、基本みんな好きだよね?」
「まぁ、細かい好みは個々人で色々とあるだろうけどね」
「じゃあ渦美のこと、好きだよね?」
「…………」
「面白くないなぁ。ノリで肯定しちゃうかと思ったのに」
しないよ。磯密さん、僕はそんな古典的なひっかけには、さすがにハメられないよ。
「ま、委員会の方はよろしく頼むわね。こればっかりは二人に頑張ってもらわないといけないから。正直、くじとかあんまり気が進まなかったんだけど、終わりよければ全てよしって言うからね」
それは、僕達なら安心して任せられるということなのかな?悪い気はしない。
「大丈夫、任せといて」
「お、随分と心強いセリフを言ってくれるじゃない」
磯密さんはそう言うと、けらけらと笑いながら去っていった。
次の日の朝、早速メアドの事について渦美さんに話を持ちかけてみる事にする。
「おはよう、渦美さん」
渦美さんは自分の席に座りながらじっと本を読んでいた。いつもどおりの光景。比較的早いせいか、教室にいる人はまだ少ない。
「いきなりだけど、渦美さんって携帯電話持ってたりする?」
「……それが?」
渦美さんは本から目を放さずに言った。
「いやさ、持ってたら番号とアドレス交換しない?ほら、委員の事とかで家に帰っても何かあったら話せるから」
渦美さんは本を開いたまま固まっている。考えているようだ。
「……そう」
渦美さんは本を閉じて机上に置くと、鞄を手に取りその中をまさぐり始めた。しかし、すぐに手が止まる。渦美さんの横顔からは何の感情も感じられない。
「……自分のアドレスを教えるなんて始めて。やり方が分からない」
ポツリと渦美さんは漏らした。
「えっと……じゃあとりあえず携帯見せてくれる?」
「……どうして」
「赤外線のヤツがついてるか見たいからさ」
「……赤外線って、何」
「ええっと……情報を飛ばす為のものかな」
日常的に何気なく使っている単語の意味を改めて聞かれると、案外うまく答えられないことが多い。これもその内に入るかもしれない。
「……そう」
渦美さんは再び鞄の中を探りだした。さらに待つこと二秒で携帯を取り出した。ストラップ等の装飾品をつけてないその携帯は、そのまま店においても違和感を持たないであろう、スライド型の携帯だった。
「ちょっと貸して」
僕が手を出すと、渦美さんは一瞬ためらったがその上に携帯を置いてくれた。僕は受け取った携帯を見てみる。すると側面に黒くて四角いものがあった。
「うん、いけるね」
「……なにが」
うん、と頷く僕に渦美さんはもどかしそうに言った。本当に何も知らないのだろう。
「ちょっと待ってね。僕の方から送るから」
「…………」
僕は自分の携帯を取り出して、アドレス帳から自分のアドレスを呼び出し、赤外線送信をした。僕の携帯の先端と、渦美さんの携帯の右側面をくっつける。
しばらくすると、彼女の携帯のディスプレイに受信完了を告げる文字が表れた。それを渦美さんに見せながら僕は作業が完了した事を報告した。
「終わったよ。アドレス帳を開いたら、僕のがあるはず」
「……そう」
渦美さんは僕から携帯を受け取り、いくつかボタンを押す。
「……ある」
「うん、なら良かった。また渦美さんからメール送ってきてね。そしたら僕も渦美さんのアドレスが分かるから」
「……そう」
渦美さんは不思議そうに携帯をくるくると目の前で回しながら見ていたが、その光景を僕が必死に笑いをこらえつつ眺めているのに気づくや否や、慌てて携帯を鞄にしまって読書を再開した。
もう用事も済んだことだし、早々に渦美さんから離れた方が良いだろう。僕は自分の席に向かって歩いた。しかし、その途中で僕はいきなり首根っこを背後から掴まれ、ズルズルと教室の外へ連れて行かれた。ちょ、苦しいんですけど。
教室前の廊下にて。やっと首根っこが開放されて、息を荒くしながら新鮮な空気を求める僕に、目の前にいた時雨が咆哮した。
「裏切りものぉぉぉぉ!」
「いや、待って。まず何でこんな事されなくちゃいけないの?っていうか、僕が何を約束して何を裏切ったの?」
「お、お前ってヤツは……恐れ多くも渦美とアド交換なんかしやがって!何で渦美も断らなかったんだよ!」
百パーセント私怨じゃねーか!と僕は言おうとしたが、時雨が僕の首を掴んでブンブンと振りまくるのでそれは叶わなかった。
「そんな、こ、と、僕、に、言われ、ても、わ、かん、ないよっ」
「くそぅ!俺なんて相手にもしてもらえなかったんだぞ!」
そ、そうですか。
「なのに、お前は何をイチャイチャラブラブよろしくやってくれてんだ!」
「そう、いう風、に、見え、て、いるの、多分、時雨、だけ、だ、と、思う、から、ね」
「あんなの見せつけられたら、俺もう明日から学校に来れねぇよ」
時雨は僕から手を離してうなだれた。
「えっと……」
「なぁ、どうやったらアイツと話せるんだ?なんでお前だけ話せるんだ?」
「わ、分かんないよ……」
「俺は今、生きてきた十七年間の中で、最もハテナな存在だ……!」
「自分の言ったこと、もう一回心の中で言い直してみようか。日本語崩壊してるから」
時雨は呻きながら頭をかきむしった。
「何だ、俺の何がいけなかったんだ!」
「じゃあ時雨は、どうやって渦美さんにその話を持ちかけたの?」
「ん?俺はな、確か……『渦美さんのを俺に下さい!』って叫んで九十度お辞儀したね」
一瞬自分の耳を疑った。
「それ、ガチ?」
「うん、ガチ。本当だぜ?本当に九十度深々と頭下げたんだぜ?」
いや、そこを疑ったんじゃないよ!僕は思わず頭を抱えた。
「そ、その反応は、あれか!分かったのか!?俺の至らなかった点が!お前天才だな!」
目を輝かせて詰め寄ってくる時雨。うわぁ近い近い、離れろ。
「ちなみに、渦美さんの反応は?」
「ギロリと睨まれて逃げられた。追いかけても良かったけど、生憎<絶対零度>の視線を直で食らったばかりだったから、そんな気力はなかったね」
「いやさ、いきなり『僕に下さい』はまずかったと思うよ。あと、『渦美さんのを』って限りなく抽象的すぎ。下手したら、お前が携帯のアドレスのことを言っていたってことすら伝わってないかも。さらに言うなら九十度お辞儀されたら僕でもちょっと引くよ」
「そうか、その部分が至らなかったか……」
僕が意見してやると、時雨は自らの過去の行動を脳内で省みているのか、目を瞑って考え込んでしまった。
「その部分って……ほぼ全部だけどね」
「ん、待てよ…………あぁ!畜生!ギリギリ九十度に届いてなかったかもしれねぇ!」
気がつけば、もうすぐHRが始まる時間になっていたので、僕は一人で悶絶する時雨を放って教室に入ることにした。
HR終了。今日も谷園先生は連絡事項を数点告げると、すぐに教室を出て行った。どこかから聞いた話だと、僕達のクラスは学年一HRが短いことに定評があるらしい。
一限目までにはまだ少し時間がある。ボーっとしながら自分の席に座っていた僕。すると、ポケットの中の携帯がバイブした。
校内での休み時間等の携帯の使用は禁止事項にはなっていないものの、例えば授業中に着メロなんかが鳴ってしまうと、先生によっては少々厄介なことになってしまう。
別に今は授業中でもなんでもないけど、僕はポケットから携帯をコソコソと取り出し、メールの受信ボックスを開いた。
見たことのないメールアドレスからこんなメールが届いていた。
『 本文:渦美怜香。テストメール』
僕は体をねじって左後方に座っている渦美さんの様子をうかがった。向こうもこちらを見てきていた。目が合うと、渦美さんはさっと目をそらした。
『 本文:了解。ありがとう』
僕は返信を送った。アドレス帳に登録する作業は後にしておこう。
一限目の開始を告げるチャイムが鳴ったので、僕は携帯を閉じてポケットにしまった。
[絶対零度にデレはない 五 終]


