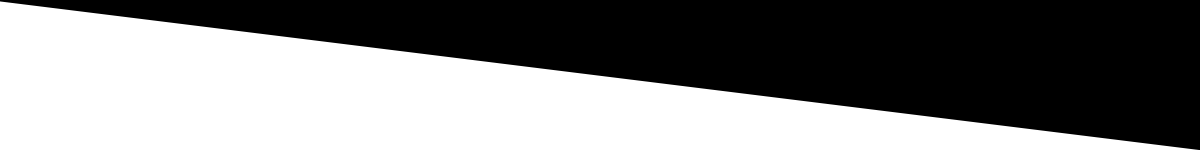
絶対零度にデレはない 六
- Absolute Zero No.6 -
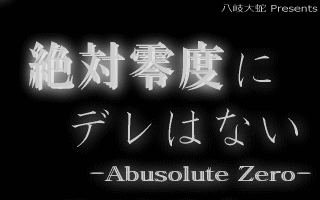
「相薙先輩、ちょっと宜しいですか?」
ある日の放課後、学園祭へ向けての設営の準備が体育館で行われており、もちろん参加していたところ、斜向さんの声がした。
「どうしたの?」
声のした方を見ると、比較的大きめのダンボールがフワフワと宙に浮いていた。……違う、ダンボールに隠れて見えてないのだ。
「ちょ、大丈夫?」
そう言いながら僕は彼女からダンボールをひょいと取った。
「わ、わ、あわわ……」
するとダンボールがいきなり消えた事でバランスを崩したのか、斜向さんはふらつく。ゴン、という衝撃がダンボールに伝わってくる。
「だ、大丈夫?顔面打ってるじゃん!」
ダンボールを置いて彼女の様子を窺う。
「うー、大丈夫れす。ちょっとおれこに当たったらけれすから……」
ろ、呂律が回っていない。ヤバイかもしれない。
「ご、ごめんね?僕がいきなり取っちゃったばっかりに……」
おでこを手で押さえながら目を若干潤ませている斜向さんに僕は謝った。
「だ、大丈夫です。も、もしも先輩が取って下さらなかったら恐らくあと十歩も歩かないうちにコケていたかと思われます……」
あー想像できなくはないかも。
「あ、そうだ、忘れる所でした。先輩、お尋ねしたい事があるんです」
「なに?」
「私って……渦美先輩から嫌われていたりするんですかね……?」
不安そうに斜向さんは聞いてきた。正直、いきなりの予想外の質問に戸惑う僕。
「この前も、話しかけただけで、すごーく怖い目で睨まれてしまいまして……」
渦美さん、後輩相手に<絶対零度>の瞳を使うのは止めようよ。
「あ、大丈夫だよ。嫌われてはないと思う」
「で、でも、私がいたら迷惑かもです……」
「渦美さんは人と話すのが得意じゃないみたいだから、悪気はないんだけど少し冷たい態度をとってしまうことがあるみたいだよ。そんなに気にしなくても大丈夫だって。もし、本当に斜向さんのことが嫌いだったら、睨みもせずに無視するんじゃないかな?」
僕が精一杯渦美さんのことをフォローしつつそう言うと、斜向さんはクリっとした目をさらにクリッとさせて小首をかしげた。
「そ、そうでしょうか?」
「うん、絶対そうだって」
「分かりました。渦美先輩の彼氏さんが仰ることですもんね。信じますです」
そう言って、今日はじめての満面の笑みを見せる斜向さん。
「はい、ちょっと待ってねー。誤解をとく必要があるようだねー」
背筋にヒヤッとしたものを感じながら、僕は諭すように言った。
「え?どういうことですか?」
斜向さんはキョトンとする。
「君も磯密さん……って言っても分からないか、僕のクラスの委員長と同様に何か勘違いしているみたいだね。僕、そんなに渦美さんと仲良くないからね。ましてや付き合ってるとか絶対にあり得ないからね。もし仮にそんな情報が広まろうものなら、僕確実にある男子生徒から呪われるね」
ある男子生徒=時雨。
「でも、仲良くしていらっしゃるじゃないですか。いつも楽しそうに話してますし」
「普通に会話してるだけだからね」
「渦美先輩が心を開いているのって、相薙先輩だけじゃないですか」
「だから……本当に何もないんだよ?」
「むむぅ、難しいですね。絶対に何かあると思うのですけど……」
顔をしかめながら考え込む斜向さん。
「まぁ、深く考えても何も得られないと思うけどね。斜向さんがそうしたいならそうすれば良いと思うよ」
「あ、それともう一つです」
斜向さんはバッと顔を上げた。
「私のこと、下の名前で呼んでもらって結構ですよ?」
「え?どういうこと?」
また、いきなり何を言い出すのか。
「ですから、紗姫って呼んでください」
突然の頼みごとにうろたえる僕。
「えっと、なんでいきなりそんな……」
「斜向って苗字で呼ばれるの、あまりすきじゃないんです……」
まぁ、斜向っていったらひねくれてる感じがあるからね。斜向さんのイメージとは少し合わないところがあるかもしれない。まぁこれは僕個人の考えだけど。
「ですからです」
「そんな事言われてもなぁ……姉を除いて女子を下の名前で呼ぶとかしたことないし」
「お願いします、紗姫って呼んでください」
ぺこりと頭を下げてくる斜向さん。
「えっと……紗姫さん?」
「さん付けなんてそんな!呼び捨てでお願いしますですよっ」
勘弁してくれよ……と、僕は言いかけたが口を噤んだ。向こうは折れてくれそうにないし、こうなったら腹をくくるしかないのかもしれない。
「分かったよ、紗姫。こう呼んだら良いんだよね?」
「おぉー」
斜向さん……紗姫が歓声をあげる。
「ありがとうございます!」
「で、このダンボールはどこに運んだら良いの?僕が行って来てあげるけど?」
僕は先ほど足元に置いたダンボールを指差して言った。すると紗姫は、初めて見せる意味深な笑みを浮かべた。
「え、どうしたの?」
「そのダンボールは、生徒会長から渦美先輩に持っていくように頼まれたものなんです」
渦美さんは、僕達がさっきいたところから三十メートルくらい離れたステージの袖にいた。後姿に声をかけてみる。後ろには紗姫がついてきている。
「渦美さん」
何かを紙に書き込んでいた渦美さんは、ペンを止めて言った。こちらは振り向かずに。
「……なに」
「えっと、紗姫が生徒会長から渦美さんに持っていくように言われた荷物を持ってきたんだけど……正直、僕には何の事だかさっぱりだけど、まぁここに置いとくね」
「……紗姫?」
渦美さんは怪訝そうな顔をしてこちらを向いた。しかし、すぐに僕の後ろに誰かいることに気がついたらしい。視線が僕の後方に移った。
「えと、私には重すぎて運べそうになかったので、相薙先輩に頼みましたのです……」
声が僕の後方から発せられる。下を向いているからか、少しこもっていた。
「……そう」
僕が床にダンボールを置く前に、渦美さんはそれをパッと手に取った。
「……相薙」
「なに?」
「……どうして下の名前で呼んでいるの?」
気づいたらしい。いや、そりゃ気づくか。さぁ何と答えるべきか。別に何も後ろめたいことは無いのだけど、少し考えてしまう。
「頼まれたから。苗字で呼ばれたくないんだって」
正直に言う事にした。
「……そう」
「もしかして、渦美さんも下の名前で呼んだほうが良かったの?」
冗談を言ってみる。もし頷かれても良い気がした。
「べつに」
<絶対零度>の瞳から放たれる摂氏マイナス二七三・十五度の視線と共に、間髪なく否定の言葉が返ってきた。
「……べつに」
もう一度彼女は繰り返す。本気で怒らしてしまったかもしれない。
「ご、ごめん!悪気は無かったんだ。気分を害してしまったなら謝るよ」
僕は手を合わせながら、謝罪の言葉を口にする。
「…………そう」
渦美さんは僕から視線をそらして言った。そして恐らく何かを言おうとしたのだろう、彼女はもう一度口を開きかけたが、また閉じてしまった。
「ご、ごめんね。じゃあ僕達は自分の持ち場に戻るから」
気まずい空気に耐えられなくなり、そう言って踵を返した時。
「……相薙」
渦美さんに呼び止められた。
「……今まで通りで良い」
振り返らなかったから表情まで見えなかったし、僕の勘違いだったのかもしれない。
「……今まで通りで、構わない」
でも、彼女の言葉は、どこか自分自身に言い聞かせている感じがした。
「わざわざ運んでくださいまして、ありがとうございました。おかげできちんと届ける事が出来ました」
逃げるようにさっきまで居たところに戻ってきた僕に、同じく逃げるように僕の後ろを走ってきた紗姫が頭を下げながら言った。
「う、うん。どういたしまして」
「渦美先輩と……喧嘩しちゃいましたか?大丈夫ですか?私が、自分で届けていればこんな事にはならなかったかもですのに……」
「大丈夫。まぁ、今日帰ってもう一度メールで謝っておくよ」
自責の念に駆られていたのか、うなだれていた紗姫だったが、僕がそう言った瞬間にパッと顔を上げて目を丸くした。
「メ、メアド交換済み……!やっぱり、先輩達って付き合っていたんですね!」
「だからなんでそうなるの。メアド交換している事が付き合っているかどうかの判断基準には絶対になり得ないからね」
「いえ、これは絶対に何かを感じます……」
真剣な顔をして呟く紗姫。僕はこれ以上何を言っても無駄だろうと思い、肩をすくめながらため息をついた。
「馬鹿ぁ!ハルの馬鹿ぁ!」
「ちょ、姉さん落ち着いて!姉さん!姉さんってば!」
「馬鹿!馬鹿!馬鹿!ハルの馬鹿ぁ!」
夕食後、リビングにて。優菜姉さんに六十七回馬鹿と罵られる。
「姉さん!今午後の九時だから!近所迷惑になるって!」
今日学校であった事を話せと言われたので話したら、こうだ。ちなみに馬鹿といわれ続けなければならない理由は、まだ話してもらっていない。
「なんで!?なんでそうなるの!せっかく良い具合にフラグ立てられてたのに!」
「落ち着いてってば!他所から聞いたら絶対に変だから!『何の旗だ?』とか思われるからさ!姉さんってば!」
現状を説明すると、僕はソファの上に寝転がっており、姉さんがマウンドポジションを取りつつ僕に拳を振り下ろし続け、それを唯一自由に動かせる両手を使って防いでいる感じだ。
「ハァ……ハァ……馬鹿……」
はい、六十八回目。
「姉さん、そろそろ下りてよ。結構キツイ」
「土下座して謝るまで下りないもん」
「何を謝るのさ。それにこの体勢じゃ土下座不可能だから。あと大学生になって、もん、は無理があるからね」
「何だとぉ!私はまだ二十歳だぞー!」
「いや、そこに食いつくんだ!?出来れば一つ目に食いついて欲しかったんだけど!」
「だって、ハルが私を年増扱いするから」
「してないからね……で、僕の何がいけなかったのさ。いい加減教えてよ」
すると姉さんは、ぶぅー、と頬を膨らませながら言った。
「せっかくフラグが立ちかけてたのに、ロリっ娘に鞍替えしたからっ」
「はぁ?」
「だーかーら!クーデレキャラの攻略が序盤から中盤に行きかけてたのに、ここに来て後輩ロリっ娘に唆されたから!」
「ま、待ってね。ロリっ娘って紗姫が?」
「その子!っていうか何で下の名前で呼んでるの!どうせ『せ、先輩!紗姫って呼んで欲しいのですぅ〜』とか言われて頷いたんでしょ!」
「若干違うけど、そうかな。普通に頼まれただけだからね。でも、なんでロリっ娘になるの?いくら小さくても高一だよ?」
プッチーン……
何かが切れる音が聞こえた気がした。
「何を言ってるの!最近は、年齢や外見だけでロリキャラかどうかなんて、判断出来ないの!『可愛くて、ちっちゃくて、童顔』って言うのは、ある意味ロリであるための十分条件ではあるけど、必要条件ではなくて、」
「はい、ストォォォップ!もういいから!もう語らなくて良いから!」
どうやら姉さんの逆鱗に触れてしまったらしい。
「もっと本質を見定めないとダメ!この場合の例に挙げられるのは、そうね……『けなげさ』とか『庇護欲を刺激するか』とか!可愛くて小さかったらみんなロリとか、そういう暴言は聞き捨てならないから!」
「いや、そんな暴言一回も吐いてないから!……あれ、ちょっと待って?可愛いかどうかなんて、僕は一切言及してないし、姉さん分からないでしょ?」
「……じゃあ聞くけど、紗姫ちゃんって可愛い?」
まぁ、どちらかと言えば、可愛い方に入るかな。十人に六、七人が振り返るくらい。
「…………えっと、」
「その三点リーダー四つ分に相当する微妙な沈黙に含まれるニュアンスは『メッチャ可愛くはないけど、十人に六、七人が振り返るレベルに可愛い』と見たぁ!」
「すげぇ!僕まだ何も言ってないのに、なんでそんな事分かるのさ!」
「だからこの前言ったでしょ!ハルの表情見てると考えてることは分かるって!」
「姉さんには絶対嘘つけそうにないね!」
こ、怖すぎるよこの人……
「二兎追うものは一兎も得ず!攻略の基本だっていつも言ってるでしょ!」
「その諺をそういう使い方をするのは姉さんだけだと思うな!あといい加減下りてくれないと、食べたものが出てきそうだよ!」
「構うものか!こうしてやるー!」
そう言って全身でのしかかってくる姉さん……をギリで止める。両手で姉さんの両腕を掴んで、必死に支えている状態だ。
「お、重!ちょ、重いって姉さん!」
「重いとは失礼な!これでも最近やせて四十一キロだぁ!」
「べつに言わなくても良いから!あと、絶対外に聞こえてるから!」
「今夜は口に出して言えないような、あんな事やこんな事をしてあげないぞー!」
「何だよそれ!っていうか、今のは絶対わざとだな!あえて外に聞こえるようにわざと大声でいったでしょ!」
「きゃ!ハルのエッチ!どこ触ってるの!」
「両腕オンリーだよ!」
「そうかそうか!お姉ちゃんのはクラスの誰のよりも柔らかいか!」
「クラスの誰よりもって何だよ!僕何もしたことないんだけど!」
「このロリータコンプレックス略称ロリコンがぁ!姉属性には興味ないってかぁ!」
「いや、もう本当に勘弁してよ!僕明日から外歩けなくなるよ!?っていうか、そのニヤニヤ笑いは明らかに確信犯だな!」
「クーデレの神様からの天罰だ!」
「いーや、違うね!姉さんからの私刑(リンチ)だね!絶対に天罰なんかじゃないね!」
そろそろ両腕が限界に近づいてきている。やばい、震えてきた……
「お、その震えは……さてはハルったら感じてるなぁ!」
「だからそんな事大声で叫ぶなって!それと違うから!断じて違うから!」
……そして、事態は急展開を迎えた。
ついに限界が来た僕の両腕から力が抜けたのだ。正直、かなり持った方だと思う。
「え?と、と、と、わきゃぁああぁあぁ!」
ドサッ!(姉) ぐほぁっ!(俺) むにゅ!(胸)
奇声を上げる姉さんが、僕の上に降ってくる姿がスローモーションで見えた。その表情に見えたのは驚愕と狼狽。きっと僕が力尽きる事は姉さん的には予想外だったのだろう。
————顔面に柔らかな感触を味わいながら、どこか遠い所で僕はそう思った。
[絶対零度にデレはない 六 終]


