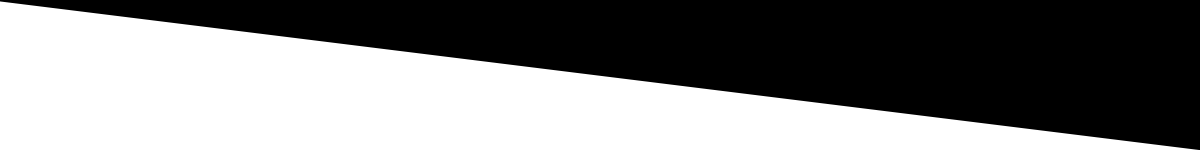
絶対零度にデレはない 七
- Absolute Zero No.7 -
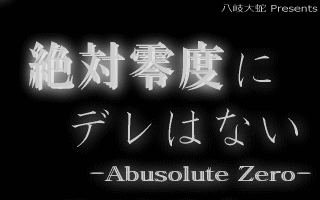
次の日の朝。昨日の姉さんとの喧嘩——ではないか、一方的にやられていた感があるし——のせいで渦美さんにメールが出来なかった事を後悔しつつ、僕は通学していた。
家からはバスと徒歩を組みあわせて四十分程度で学校に着くので、結構近い方の部類に入ると思う。バスも学生定期を使っているので、経済的にもそこまで負担にならないし。
最近は、やっと秋らしくなってきた。天気予報によると、最高気温が二十度を超える夏日がまだしばらくはそうだ。もうすぐ衣替えの季節だが、長袖にはまだ早いだろうけど、半袖では少し肌寒くなるかもしれない。
さて、昨日のあの後だけど、姉さんがマジ切れした。向こうからのっかかって来たのにこちらが怒られるのは納得いかない。マウンドポジションをとられてたから、ほとんど何の反撃も出来ずに殴られっぱなしだった。頭に拳が飛んでこなかったのは、せめてもの姉さんからの配慮だろうか。
と言ってもまぁ、全くの無益だったわけでもないのだから良いかなとも思う。顔面に残っている柔らかーな、ふにふにーっとした、筆舌尽くしがたいあの感触は一生忘れられないだろう。レア度高すぎだったね、あのイベントは。姉さん意外と大きかったんだな……普段は何も思わなかったけど。ア、アレってやつかな。か、隠れ巨……
「おっはよーっす!」
「うわぁぁぁぁ!」
いきなり肩を叩かれてマジでビビッた僕。いや、本当にびっくりした……
「な、何いきなり大声出してるんだよ……チビるかと思ったぜ」
「ご、ごめん……」
それはこっちのセリフだよ、という言葉を飲み込んで、謝っておく。
「なんだ?エロい事でも考えてたか?」
ニカニカと笑いながら時雨は言う。ひ、否定出来ないよね。今回に限っては。
僕が何も言わずにいると、時雨は意外や意外、という表情になった。
「あれ?否定しないの?……あーそうか、お前も男だったもんな、うんうん」
それを言うなら、お前も男だもんな、じゃないのか?その言い方だと「普段は女だと思っていたけど、あ、そうか、お前ってそういや男だったよね」的なニュアンスになるから。その扱いはさすがに傷つくから。
「いや、そんな満足そうに頷かれても……」
「どうした、いつものキレの良いツッコミが無いぞ?やっぱり何か考えてたな?」
「おい、見ろよ。あの娘可愛いぞ」
僕達の十メートルくらい前方を歩く知らぬ女子高生を指差し、時雨に話を振る僕。いつものこいつなら、ホイホイ乗ってくれるはずだ。そうしたら話題をすりかえて……
「今の最優先事項は、お前が何を考えていたかを突き止めることだ。妄想か?実際にあったことだ?まずはそこから言ってもらおう」
なん……だとっ!?
「お前、姉貴いたよな?」
「い、いるけど」
「ってことは……現実で何かあったって可能性は、ゼロではないな」
あれ?コイツこんなに賢かったっけ?
「よし、昨日の家に帰ってからの行動を全部話してくれ」
「いや、もうちょっと絞れよ!そんな簡単に言えることじゃないから!」
思わず声を荒げて突っ込んだ。
「じゃ、昨日のお前の姉貴との出来事を話してくれ」
あ、しくじった。
「えぇっと、まぁ色々とね……」
視線を宙に彷徨わせて、必死に言葉を探すがなかなか良いのが見つからない。
「何があったんだよ!教えろよ!」
僕の動揺を察知してか、ここぞとばかりに食いついてくる時雨。
「テ、テトリスしてた」
自分でもビックリするような嘘が、口から勝手に裏声で出てきた。
「テ、テトリスだとぉ!?」
クワッと目を剥きながら声を上げる時雨。
「そ、それは、あの、上矢印を押したら、高速落下するゲームのことか!?」
……テトリスに対するお前の認識の仕方に違和感を覚えるのって僕だけ?
「そうそう、テトリス。姉さん強くてさ。負けっぱなしだったよ」
ちなみにこれは実話である。姉さんはテトリスがめちゃくちゃ強いのだ。
「い、良いなぁ……俺の弟なんてバトルモードで一分も持たねぇぞ。相手にならない」
「そういえば弟いたっけ?」
僕がそう聞くと、時雨は顔をしかめながら言った。
「あぁ。今年で中一になったんだがな。もう嫌になるくらい弱いのよ。いやー是非お前の姉貴と一回お手合わせ願いたいね」
「休みの日だったら……家でゴロゴロしてる事がほとんどだから、相手になってくれるんじゃないかな?」
「そうかそうか!じゃあ今日家に帰ったら早速特訓しなくちゃな!」
時雨はグッと親指を突き立てる。
「頑張れー」
「おう!あ、そういや今日は早めに教室に行かなきゃいけないんだった。ちょいと野暮用があってな!それじゃ、また教室で!」
そう言うと時雨はダッと走っていってしまった。
結論。やっぱりアイツは馬鹿だった。
僕はあくびを一つして、学校に向かう足を速めた。
教室に入ると、磯密さんに手招きされた。なんだろう。
「おはよ、相薙。ちょうど良い所に来てくれたね。カモンカモーン」
「あ、おはよう。……ちょ、ななな何だよ」
腕を引っ張られ、つっかえながら連れてこられたのは磯密さんの座席だ。廊下側から二番目の列の、一番後ろの席。
「鞄、置いてきて良いかな?」
「大丈夫大丈夫。置いてこないと死ぬわけじゃないんだから」
鞄で生死が分かれるわけ無いだろ。言おうかと思ったが、何か急いでいるみたいだし、止めておく。急用だろうか。
「今日のホームルームで私達のクラスの出し物何にするか決めるでしょ?」
「あー、先生昨日そんな事言ってたね」
「でさ、何か良い案ない?そのまま使わせてもらうから」
実は、クラスの出し物の件で、今日のHRで磯密さんがいくつかの案を出してその中から適当に決めようぜー、という流れになっているのだ。
なぜこうなったかというと、昨日も一応話し合いの時間は設けられたのだが、何も意見が出なかったので、これはまずいと思った担任が委員長に幾つか案を考えてきてもらい、その中から多数決を取ろうと提案したのだ。そしてその案が賛成多数で可決されたと。
「……参考にするんじゃなくて?」
「使わせてもらうからさ。二つ三つばかりお願いっ」
一切の後ろめたさを感じさせない笑顔で言ってくる磯密さん。
「……職務放棄?」
僕はジト目で磯密さんのことを見た。
「いや、よく考えてみなよ。相薙の意見が高確率で反映されるんだよ?損はないよ?」
そういう問題じゃないからね。
「二つ三つねぇ……うーん」
「出来るだけ低予算で、クラスのみんなに公平に色々な役が回ってきて、喧嘩とか揉め事とか起きにくくて、みんなで団結出来て、現実味が高い案が良いな」
「要求レベル高!あつかましっ!」
「だから、喫茶店とかは難しいかも。準備に少し手間がかかるかし、自分ひとりくらい抜けても大丈夫だろうって考える人も出て来易いから。団結しにくいかもしれないしね」
「な、なるほど」
さすが委員長。きちんとこういうことは考えているみたいだ。
「だからメイド喫茶とかもなし。私としては渦美がメイドさんの格好してる所とか見てみたかったけど……さっき自分でつけた縛りに引っかかっちゃうね」
ちょ、姉さんみたいなこと言わないでよ磯密さん。……っていうか、渦美さんがメイドってどんな感じなんだろうか。
「あ、妄想してる。真剣な顔で妄想してる」
ケラケラ笑いながら磯密さんは言う。
「な、あ、ち、ちが」
しまった!ハメられたか!
「それより!僕から意見を言わないといけなかったんじゃないかな!?」
必死に話を戻そうとする僕。
「あー分かったわよ。『渦美は僕のメイドだから、あいつが喫茶店で名も知らぬ客連中に愛嬌を振りまくのは耐えられない』って?なら仕方ないわね。却下にしましょう」
「言ってない!僕、そんなこと一言も言ってないから!」
ブンブンと首を横に振りながら猛烈な勢いで否定する僕と、それを見てお腹を抱えながら笑っている磯密さん。第三者の目から見ると、さぞかし朝から賑やかな光景だろう。
「いやー、相薙は面白いね。話していて退屈しない」
磯密さんは目尻に浮かんだ涙を指で拭いながら言った。
「そ、そう?そんな事始めて言われたけど」
「まぁ人それぞれだろうけどね。それで、何か良い案ある?」
磯密さんの表情が真剣なものになった。ここからは真面目な話し合いになるのだろう。
僕はいくつか適当な案を言った。この前時雨が言っていたヤツも混ぜておく。
「なるほど。私としては、鬼ごっこ的なのが良いかもって思う」
お、時雨案だ。
「あとは……お化け屋敷は定番だし、セッティングとか衣装とかが大変だけど、やりがいはあるし、やる事が多い分手持ち無沙汰になる人は少なくなりそうよね。それに結構人は入っているみたいだし」
「毎年お化け屋敷はどこも盛況だよね」
「ありがと、じゃあこの二つを使わせてもらうわね」
「了解。やっぱりそのまま使うんだ」
「大丈夫、私もちゃんと一つ考えるから」
そう言って胸を張る磯密さん。いや、そんな自慢気に言えることじゃないからね。
磯密さんから解放され、自分の席に鞄を置く。ふと後ろを向くと、いつの間にか渦美さんが来ていた。僕は声をかけてみることにする。
「おはよう、渦美さん」
今日は本を読んでいなかった渦美さんは、チラッとこちらを見てきた。
「えと、昨日はごめん。改めて謝っておこうと思って」
「……そう」
素っ気ない返事がきた。
「……相薙は、」
渦美さんは目を逸らしながら言い淀む。
「…………なんでもない。今、話す必要のないこと」
「そ、そっか」
僕は返答に困ったので下を向いた。僕達の間に数秒ほど沈黙が流れる。
「……携帯。変なのが出てくる」
いきなり渦美さんが意味不明なことを言ってきた。僕が顔を上げて困惑していると、彼女はスカートのポケットから携帯を取り出してピッピッと幾つかのボタンを押した。
「……これ」
渦美さんから無表情のままクイッと差し出された携帯を受け取る。液晶画面を見てみると、メール作成画面になっていた。画面のした半分には絵文字の欄が表示されている。……ひょっとしてこれのこと?
「……このボタンを押すと、訳の分からないマークや記号が出てくる」
渦美さんは、シャープボタンの上に置かれた自分の人差し指をじーっと見た後、少し不安そうな瞳を僕に向けてきた。
「……買い替えるべきか、修理に出すべきか、そのままで良いのか、分からない」
「えっと、これは絵文字って言ってね。文章だけだと素っ気ないでしょ?まぁ、使い方は色々あるんだけど、難しいかな?」
「……分からない」
僕は乏しい語彙力をフルに活用して、絵文字や顔文字についてタラタラ説明してみた。
「……少しだけ理解できた気がする」
少しかよ。まぁ少しでも理解してくれたなら良いか。
「……つまり、文章では表現しきれない感情の起伏などを表すと共に、文章を装飾する為のものであり、同じ一つの記号でも文脈によっては異なる使われ方がある場合も存在する……ということ?」
「そ、その認識で十分だと思うな」
僕の説明よりも、よっぽど簡潔で分かりやすいと思う。
「……辞典とかはあるの?」
「へ?」
思わず間の抜けた声が出てしまう。じ、辞典って何さ。
「……だから、絵文字の使い方とかが載っている辞典とかはあるの?」
「『絵文字顔文字大全』……みたいな?」
僕が適当な辞典名を捏造して言うと、渦美さんは真剣な顔をして頷いた。僕は吹き出しそうになるのを必死にこらえる。
「僕は見たこと無いな。そもそも絵文字あまり使わないしね」
「……そう。…………何がおかしいの?」
渦美さんの目つきが少し鋭くなった。ヤバイ、表情に出てしまってたかな?
「べ、べつに何もおかしくないよ?」
「……嘘。絶対笑ってる」
渦美さんが睨んできた。<あの>瞳ほどではないが、少し背筋が凍る。
「と、とにかく、絵文字は慣れというか、使って覚えるものだから。頑張って」
「……そう」
「携帯持つの、初めてなの?」
僕が聞くと、渦美さんはしばらくの沈黙の後、小さく首を立てに振った。
「じゃあ分からなくても仕方ないか」
「……その言われ方は、見下されている感じがするから嫌」
「あ、ごめん。えっと……また何か分からないことがあったら、僕で良ければ聞いてね」
彼女は頷くと、席を立って教室から出て行ってしまった。
家庭の事情はそれぞれあるとは言え、携帯のない中学生活か……中学から持たされていた僕には想像できないなぁ。
家に帰ったら渦美さんにメールしてみようかなと思いつつ、僕は一限目の用意をするべく自分の席に戻ることにした。
[絶対零度にデレはない 七 終]


