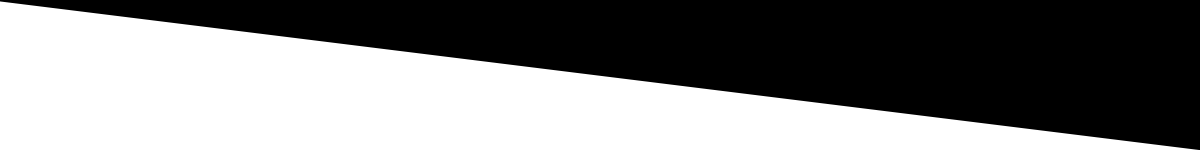
絶対零度にデレはない 九
- Absolute Zero No.9 -
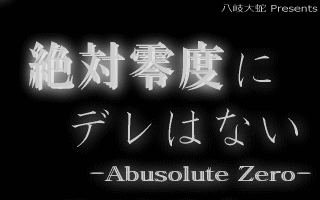
いくつか階段を下りて、目的もなく校内をブラついていた僕は、こちらに向かって歩いてくる二人の少女の姿を捉えた。
「あ、相薙先輩!」
片方の少女がペコリと頭を下げた。紗姫だった。隣にいるのは友達だろうか?
「こんにちは、紗姫」
「こんにちはです、先輩。えっと、この子は友達のマミちゃんです!」
マミちゃんとやらは、上目使いに僕を見やりつつ、ムスッとしながら頭を少しだけ下げた。朱色の髪がサラリと揺れる。まるで少年のような出で立ちからは、ほどよく日焼けした手足がすっと伸びていた。
「い、一条真海です」
「それより、この人だよ。ほら、あの渦美先輩と色々噂されている人!」
紗姫がそういうやいなや、
「そ、そうなんですか!?」
一条さんの表情が一瞬にして驚愕と畏怖の色に変わって行く。足が僅かにガタガタ震えているんだけど、大丈夫かな?
「え、あ、その、あ、あ」
口をパクパクさせながら一条さんは言葉になっていない音を発する。
「その、そうとは知らず……いや、知ってはおりましたがピンと来ず……いやいや、言い訳なんて以ての外ですね!先程は、とんだご無礼を致しました!その、ああ相薙先輩、相薙先輩なんですね!把握しました!私、1年D組の一条真海と申します!」
そ、そんなにテンパらなくても!?
「そ、その、渦美先輩とは先日ゴールインされたとか!さ、先を越されて悔しい限りですが、さすが相薙先輩です!私など足元にも及びません!」
「ちょっと待ったぁ!」
たまらず声を上げる僕。一条さんの体がビクッと強張る。
「はい、なんでしょう!」
「ゴールインって何!?一年生の間では僕達は何処まで行った設定になってるの!?あと、先を越されて悔しい限りって、その、あれ!?」
動転しすぎてセリフの最後の方がかなり適当になってしまったが、気にしない。
「はい、お答えします!……と言いたいところですが、その、申し訳ないです。ちょっとこのような公の場所では言いにくい事でして……」
そう言うと、髪の毛に負けず劣らず顔をポッと朱色に染める一条さん。
「そこで顔を赤くしないで!ごめん!何か謝っておかないと気が済まなくなった!」
最初は「ちょっとボーイッシュな感じな子だな〜」くらいの第一印象だったのが、今では頭の中でガンガン警鐘が鳴り響いている。初対面の後輩を相手に言うのもなんだが、かなりの危険人物かもしれない……
「紗姫からは色々と話は聞いております!」
「あわぁー!先輩は気にしなくて良いです!マミちゃんも余計な事言わなくていいよ!」
慌てふためく紗姫。いや、気にしなくて良いと言われても気になるよ。
「そ、そうなのか?でも、一応相手には伝えておいた方が良いかなと思ったんだけど」
「そう言うのは別に言わなくても良いの!」
「う〜ん……」
不満そうに首を傾げる一条さん。
「ね、先輩!マミちゃんって、面白い子ですよね!」
こちらはいつもと変わらずニコニコ笑顔の紗姫。あ、コラ、話題そらそうとするな。
「いや、面白いとか面白くないとかで判断して良い事じゃないと思うけど……」
「相薙先輩、その、先輩が望むのならば、不肖一条真海が……」
「いえ、結構です!」
まだセリフの途中だったようだが、恐怖心から反射的に断わってしまった。
つ、疲れる……!まだ二時間目が終わったばかりだというのに、普段一日に消費するエネルギーを使いきってしまった気持ちだ!
「それにしても、相薙先輩すごいですね!いろんな所に噂で広まっているですよ?」
「あのね、紗姫。それは決して凄い事なんかじゃないからね」
「さすが相薙先輩!渦美先輩とゴールインしても、あれです、蹲踞な姿勢ですね!」
「僕、剣道部!?それを言うなら謙虚だから!……って自分で言っちゃったよ!」
気を取り直して。
「えーっと、一条さんは何かスポーツでもやってるのかな?」
こうなったらこちらから普通の話題を振ることにしよう。
「はい、お答えします!私一条真海、現在女子硬式テニス部の一部員として、コート整備や先輩方の雑用、ダブルスでの県大会出場を目標に日々練習に励んでおります!」
県大会出場を目標に日々練習に励むことより、コート整備や先輩方の雑用の方を先に言うってどうよ、という言葉は飲み込む。まぁ一年だし、雑用の方が多いのかもしれない。
「この前の地区予選で、ベスト4に残ったんだよね。コーチからは、一年ではよく頑張った方だって褒められていたよね」
「いや、まだまだ未熟な所もあるからな。気を緩めずに練習を続ける必要はある」
一条さんは紗姫にそう言うと、僕の方に向き直った。
「ちなみに、コート整備がきちんと行き届いていなかった、先輩方の要望に答えられなかった等のミスを犯した時には、先輩方からテニスラケットでお仕置きされるのです!きちんと自分の仕事はこなしつつ小さなミスわざとして、お仕置きされるのが日課に……」
「ちょっと待ってね!こういう場合は、競技用のテニスラケットを使って後輩をお仕置きする先輩を突っ込むべきなのか、先輩にお仕置きされる為にわざと小さなミスを犯す後輩を突っ込むべきなのか、どっちだ!?」
「両方……じゃないですか?」
紗姫はきょとんとした顔で言った。
「相薙先輩、恐縮ながら反論させていただきます!先輩方は、競技用のテニスラケットでお仕置きするのではなく、コーチには知られていない用具庫の隠し抽斗にしまってある、『調教用』のテニスラケットできちんとお仕置きして下さるのです!」
「あるんだ!?調教用のがあるんだ!?なんか今まではそうでもなかったけど、女子硬式テニス部がすごく遠い存在に思えてきたよ!」
「えっと……男子禁制ですからね」
「違うんだ、紗姫!そういう意味で『遠い存在』って言ったわけじゃないんだ!」
「はい!ちなみに、面も良いのですが、取っ手のテープがぐるぐる巻きにされた硬い部分が“垂涎の一品”なのです!」
「これから先、グルメリポーターとかが“垂涎の一品”という言葉を、おいそれと使いにくくなるような発言は止めようか!」
「はい、以後気をつけます!」
ここで僕は深呼吸する。荒くなった呼吸を整える。なんというか、もう駄目だ、ついていけない。一刻も早くこの場から逃れたい!
「えっと、ふと思ったんだけど、どうしてそんなに独特な敬語を使うの?べつに、お答えします!とか言ってから発言しなくても良いんだよ?」
「はい、お答えします!しかし、口癖と言うのはなかなか直らないものなのです!」
まぁ、そりゃそうか。
「私とは普通にしゃべるのにね」
「そりゃあ、紗姫は同い年だし、友達だからな。相薙先輩は、先輩だからこうなる」
「い、色々大変なんだね……」
僕がそういうと同時に四限目の開始を知らせるチャイムが鳴った。思わず安堵の息が漏れる。やっと開放されるのか……ちょっとテンション上げすぎちゃったな。
「あれ?先輩、教室に戻らなくて良いのですか?」
紗姫の言葉にハッとする。しまった!ここからだと、僕の教室まで走っても十五秒くらいかかる!しかも次は移動教室じゃないか!
「まずい、教室が閉められる!じゃあね!」
早々に退散する僕の後ろを追いかける形で二人の声がした。
「はーい、頑張ってくださいです!」
「はい!相薙先輩なら、必ず間に合うと確信しております!今度よろしければ是非……」
一条さんの言葉の最後の方が聞こえなかったけど、まぁ良いか。なんか怖いし。ゴールインの件とか、色々聞きそびれたこともあるけど、これもまぁ、また今度で良いか。
昼休みになった。先程の紗姫と一条さんとの会話で疲弊しきっていた僕には、三限目終了チャイムがこの上ない福音に聞こえた。
僕の高校では、五十分授業が午前に三コマ、午後に三コマ展開されている。放課後は補講に引っかかっていない人は部活に勤しんだり、家に直行したりする。僕は後者。
「いやーヒヤヒヤしたね。まさか何も言わずに保健室にでも行ったのかと思ったぜ」
目の前でカリフラワーを頬張る時雨。彼と机を合わせて昼食を一緒に食べるのは、さっきの一条さんのお仕置きではないが、これこそ日課になっている。
あの三限目のピンチだが、僕が走って教室の前に行くと、時雨が自分の教材と僕の教材を持って待ってくれていた。教室の鍵は閉まっており、彼が言うには二、三分前には施錠係が持って行っていたらしい。全員が音楽か美術なので、教室は閉め切るのだ。
「あの時は本当に助かったよ。ありがとう」
僕は改めてお礼を言う。時雨がああしてくれていなかったら、職員室前にわざわざ鍵を取りに行かなきゃいけないし、遅刻した理由も説明しなきゃいけないし、厄介だった。
「あぁ、あのあと、乾先生には『腹痛でトイレ行ってました、ごめんなさい』って言ったら普通にスルーしてくれたもんな」
乾先生とは音楽の先生だ。僕と時雨は、音美選択で同じ音楽を選択している。
「あれは助かったよね」
「でも、なんで遅れちまったんだ?何か理由があるんだろ?」
魚の骨をご飯に立てながら、時雨は問うてきた。いや、何してんのお前。
「うん、まぁね。ちょっと後輩と話してた。実行委員で知り合った子と、その友達」
僕は苦笑しながら時雨にあの時のことを説明した。
「気がついたらチャイム鳴ってさ。あれは心臓が止まるかと思ったよ。後悔したね」
「ま、そんなことも生きてりゃ一度や二度はあるわな。気にするなって」
そういって時雨はニヤリと笑った。
この日の午後は特に何もなく、平穏に時間が過ぎていった。そして、下校。
リビングで姉さんがブリッジをしていた。
「あ、おかえりー」
「……何この出オチ」
家に帰ったら、二十歳の姉がリビングでブリッジしながらこちらに歩いて(?)来られると、弟として少し悲しくなる。
「違うよ、ロンドン橋モードだよ」
姉さんは言った。頭に血が上っているのか少し顔が赤い。
「あー分かった分かった」
「ぶぅーハルが冷たい〜」
姉さんに背を向けてリビングを出ようとすると、ドンッと音がした。姉さんがロンドン橋モード(自称)を解除したのだろう。
「ハル、今日は一段と疲れたって顔をしているね」
「ん?そう?」
僕は姉さんの方を振り返る。
「新しい出会いがあったって顔もしてる」
僕はギョッとする。何で分かるの?
「で、どんな子だったの?」
姉さんは興味津々な顔をしながら小首を傾げてきた。新しい出会いがあった事を前提に話を進めている所を見ると、自分の予想が的中していると確信しているらしい。
「えっとね……紗姫の友達だった」
「ほうほう、どんな話をしたの?」
え?あの話を再現しろと?
「難しいな……一条真海さんって言う子らしいんだけど、女子硬式テニス部に所属してるらしくて、受け答えははっきりしていて、ボーイッシュな感じだったよ」
嘘は、ついていない。
「ボーイッシュ……」
姉さんの左目が光った。
「ハル?詳しく、説明してくれるかしら?」
「何でいきなり語尾が『かしら』になるの!?あとジリジリ詰め寄ってこないで!」
「詳しく、説明してくれるかしら?」
「いや、大事な事なので二回言いました的に繰り返されても!」
僕はガッと手首を姉さんに掴まれて、リビングのソファに連行される。僕が右側に座って、姉さんが左側に座った。腕はがっちりキープされたままだ。
抵抗しても仕方がないので、僕は端折ることなく紗姫と一条さんとの一連の会話をツラツラと述べる。
「うーん……」
残念そうに唸りながら、姉さんは言った。
「ボクっ娘+ツンデレ要素があれば私的にはストライクゾーンだったんだけど……」
「姉さんの好みとか聞いてないから!ま、まあ世の中上手くいかないってことだね!」
「そうだね……でも、面白い子じゃない。今度テニスラケット買ってきてあげるね」
「いらないから!一条さんは部活の中のお仕置きで満足しているみたいだし!」
「面の良さもしっかりと教えてあげなさい」
「姉さんまでそんな事言わないでよ!せっかく一条さんから解放されて安心してたのに、
家に帰ってからもこの手のネタ振られるとか精神的に持たないんだけど!」
「ま、今日の所はこの辺で勘弁してあげましょうか」
姉さんはフフッと笑う。
「な、何その超意味深な言い方と笑い方!?」
「明日はなんと言っても渦美さんとのフラグが立ってるからね。今日は早く寝なさい」
「あぁ、その事か。今日は色々とありすぎて頭になかったよ……」
「ま、頑張って来なさいな!バッドエンドに持って行ったら承知しないからね!」
「だからゲームじゃないってば」
恒例のツッコミである。
「もしバットエンドになったら……」
声音を少し低くして姉さんは言った。
「テニスラケット買い与えた上で、一条さんとのフラグを立ててもらうから……」
「止めて!そんな恐ろしい事言わないで!」
僕は頭を抱えながら叫んだ。
「一条さんが『女子硬式テニス部はもう辞めました!相薙先輩でなきゃ嫌です!』って言うまで私は許さないから……」
「……いや、一条さんはダブルスでの県大会優勝を目標に、テニスも頑張ってるよ?お仕置きされる為だけに部活に行っているわけじゃないし、それはきちんと酌まないと!」
この一セリフだけ抜粋すると、さぞかし変な文章だろう。でも僕は、これだけはちゃんと言っておく必要があると思った。
「…………あー、ごめん。ちょっとふざけすぎたね。ごめんなさい、失言でした」
姉さんは頭を下げて、微笑んだ。
「やっぱりハルは優しいね。そういう所はちゃんと咎めるんだ。うん、姉さん安心した。というか、ハルの事がもっと大好きになったよ」
ね、姉さん……
「いや、僕もちょっとキツい言い方しちゃったかも。ごめんなさい」
僕も謝る。姉さんはニコリとした後、ガバッと横から抱きついてきた。姉さんの甘いシャンプーの香りが僕の鼻腔をくすぐった。
「でもね……」
「うん?」
僕が聞き返すと、姉さんは僕の耳元に唇を近づけて、こう続けた。
「……バッドエンドならテニスラケットを買い与えるって所までは、本気だよ?」
「ぎゃぁあぁぁあぁ!お慈悲おおおぉぉ!」
午後六時半、相薙家から絶叫が木霊した。
翌日の放課後。ついに運命の時が来た。
今、僕は一人で校門の前で佇んでいるわけだけど、事の成り行きを説明すると、終業の挨拶が終わって渦美さんの所に行くと「……少し用があるから、校門前で待っていて」と言われて、こうしている恰好だ。しかし、渦美さんも何で校門前なんかをチョイスしたんだろう。今は下校する生徒のかなり多い時間帯だし、要するに人目も多いわけだから、かなりまずい気がするんだけど……僕の気にしすぎなのだろうか。
しばらくボーっとしていると、目の前に人影がスッと現れた。
「……お待たせ」
渦美さんだった。
「あ、もう用事は済んだの?」
渦美さんはこくりと頷いた。
「えっと……それじゃあ行こうか?」
渦美さんはもう一度頷いて、スタスタと歩き出した。ぶっちゃけた話、それじゃあ行こうか、とか言っておきながら彼女の目的地がどこであるのかとか、全くもって知らされていないのだ。必然的に彼女の後ろについて行く形になる。歩くこと数分。
「……タクシーに乗る」
ポツリと渦美さんは行った。タクシー?結構な遠出なのだろうか?
「う、うん。分かった」
何を話したら良いのか分からない。気まずい雰囲気が流れる。下手な事は口に出来ないし、だから言って何も話さないのもどうかと思うし……と必死に頭を使っていると、渦美さんが突然手を挙げた。
気がつくと僕たちの横に一台のタクシーが停車した。あ、呼び止めたのね。納得。
渦美さんが先にタクシーに乗り込んだ。僕もその後に続く。
[絶対零度にデレはない 九 終]


